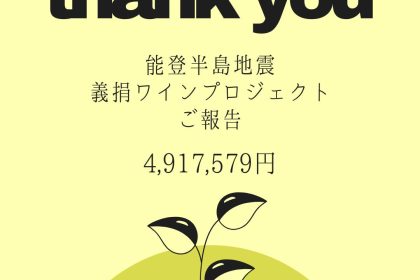おいしさの起源 その2
“おいしさ”は、嗜好という言葉に頼らなければならないほどに人によって差のあるものなのか。それとも、ある種の普遍性は存在するのだけど、我々自身のなんらかの感覚の欠如(身体の声に素直に耳を傾けられる能力、想像力、謙虚さなど…)によって、その核心部分にアクセスすることができず、周りをグルグルしているだけなのか…。
そもそも、“おいしさ”とはいったい何者で、どこから来た子なのでしょうか? はい、ようやくタイトルにまで戻ってきました(笑)。
文明が生まれるよりも遥か昔、ヒトの中に、今現在の“おいしい”に繋がる感覚、感情が芽生えたのは、どういったものを食べた時だったのか? そんなことを少し考えてみたいと思います。その当時のヒトにとっては、生き抜くこと自体が非常に大変な事だったはず。外敵や自然の猛威から身を守りつつ、命を繋ぐための糧を得ることに必死だったとオータは想像しています。そんな状況下で食べ物に求めることはと言えば、
・食べられるかどうか(毒性がないか)
・生きていくために必要な各種栄養素を含有しているか
・消化吸収しやすいか
だったのではないでしょうか。
それまでに食べたことのない(食べ)物に遭遇、まずは鼻と舌を頼りに可食かどうかを判断し、実際に食べてみて(咀嚼して飲み込む)、身体がエネルギーに満ちてくるのを実感し、格段のトラブルもなく消化できたことを確認…。このような経験を積み重ねていくうちに、「あ、これって前に食べたことあるやつだ! あの時は、これのおかげでしばらくのあいだ飢えを凌げたんだよなぁ…。それでは早速いただきます! (むしゃむしゃ…)そうそう、これこれ! この味!! またしても生かされちゃうなぁ!!」というような、過去にあったポジティブな感覚を追体験するケースが増えていったのではないでしょうか。そんな時、生き延びるための力(栄養)を与えてくれると確信できた食べ物に対して抱いた感情が、“おいしい”の始まりだったのかと。
以前に書いた「料理の起源」ともこのあたりでリンクしてくるのですが、狩猟や採集をして得たものをそのまま食べるよりも、より多くのものを食べ物とすることを可能にし(生のままだと毒性があるものを、調理を施すことで無毒化する)、より安全に、より効率的&効果的に栄養素を摂取できるようにしたものこそが、“元祖おいしい料理”だったのではないでしょうか。ヒトは、火を駆使することができるようになるのとほぼ同時に料理を始めたはずで、料理はヒトに食の面での安全性や機能性だけでなく、暖をも提供してくれます。オータ家を訪ねに来たことのある方ならご存知かもしれませんが、オータ家の暖房は薪ストーブ1台でまかなっています。住み始めて最初の冬は、薪をちゃんと乾燥させていなかったせいで、本当に苦労をしました…。その時、“ひもじさ”は飢えと寒さで感じるものなのだという事を痛感しましたし、昔のヒトもきっと一緒の気持ちだったのでしょう。こんな事を書いているこの瞬間オータの頭の中では、レキシの名曲“狩りから稲作へ”の“忍び寄る恐怖 冷えと飢え~”という歌詞がリフレインしております(笑)。少々脱線しましたが、おいしい料理とは、暖(≒熱)や機能性など物理的エネルギーをもたらすのと同時に、安心感などで我々の心をも満たしてくれるものだったのかと…。
料理を覚えたことで、短時間&最小限のエネルギー消費で莫大なカロリーを摂取することができるように、そして農耕を始めたことで、完全な形ではないにせよ飢えの不安から解放され、その恩恵に与る形でヒトは、学問、芸術、スポーツなどの様々な文化に彩られた文明を開化させていきます。それまでのヒトは、他の動物同様に種族保存本能や生存本能に従って、種としても個としても生き延びることを目的に生きていたわけですが、文明文化を進化させていくうちに、それ(生き延びる)以外の事にも、生きる意味ないし動機を見出し…。何かしらの芸術に魅せられた人もいたでしょうし、この世界の理を理解すべく学問を志した人もいたのでしょう。
文明化以前のヒトにとっては、自身の生命や種の保存ないし繁栄を脅かすことだけがストレスの対象だったと言って良いと思うのですが、文明が進むにしたがって、社会的な役割もどんどん細分化&分業化され、社会もヒトの精神構造も複雑になっていき、その結果として原始時代のヒトが感じることがなかった別の類のストレスが現れてきたのだと想像しています。
そして分業化が、提供する側とされる側という関係性も生み出します。そして、ヒトは提供される側にまわった際に、肉体的なものだけでなく精神的な休息、平穏、癒し、充電などといったものも受け取っているのでないでしょうか。
我が心の師匠は、「文化は心の栄養」と評していましたが、まさしくその通り!!
ライブ感や一体感、グルーヴ感などを醸成するためには、ある程度密になることが必要不可欠なエンターテイメント(オータ個人としては、レストラン業もこのカテゴリーに属すという認識です)を享受することがなんとなく憚られる時代を我々は今現在生きているわけですが、社会から娯楽が(ほぼ完全に)消え去った時に、ある種の空虚感や息苦しさを覚えたのはオータだけではないはず。これが意味することは、我々ヒトは生き延びるためだけに今を生きているのではなく、感動、興奮、歓喜などポジティブなものだけでなく悲しみや苦しみなどネガティブなものも含め、ありとあらゆる“生きた”感情に出逢い、そこから“生”を実感したくて、生を繋ごうとしているということなのかと。
ヒトがヒトとして生きていくという事は、生き延びることだけでは不十分で、人生を謳歌するという事が肝要。そのためには、身体に対して物理的なエネルギーをチャージするだけではなく、心にもさまざまな栄養をチャージする必要がある…。とはいえ、これほどまでに文明が進歩した今現在でも、残念な事に飢えや貧困が完全になくなったわけではなく、生き延びることでさえ困難なヒトも相変わらずいるという現実があるわけで…。ヒトらしい生活を享受できていること自体が、考えられないくらい素晴らしい事なのだと、感謝の念を抱きつつ我々は生きていかなければならないとオータは思うのでした。
つづく