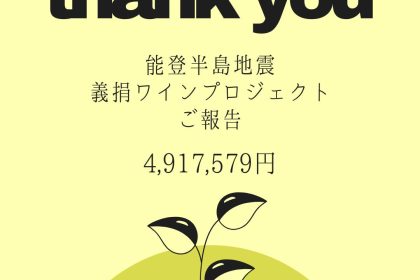ヴィナイオータ かわら版 ~石橋編 その四~
石橋の“飲んでもらいたい”ワイン紹介!!
はる‐さめ【春雨】
1春、しとしとと静かに降る雨。しゅんう。《季 春》「―やものがたりゆく簑と傘/蕪村」
2 緑豆のでんぷんから作った透明な麺状の食品。吸い物・酢の物・鍋物などに用いる。ジャガイモなどを原料としたものもある。
(大辞泉より引用)
(*この文章は2020年3月末に書かれたものです。)
春ですね。東京では、統計開始以来最速で桜の開花宣言がされました。陽気の高まりは、どんなに人間社会が混沌としていても春はやってくるのだと感じさせます。そして、桜といえば花見。花見といえばお酒ですが、今年は花だけが咲き誇るのでしょうか。抗いたいところです。
春は雨の多い季節でもあります。「菜種梅雨(なたねづゆ)、桜雨(さくらあめ)、春霖(しゅんりん)、催花雨(さいかう)」など色々な呼び名があるようですが、どれも乾燥した冬から草木の芽を張らせ、花を咲かせる春に降る雨を時期や降り方によって表現を変えているようです。そして、「春雨(はるさめ)」は、仲春から晩春にかけ、しとしとと細やかに降り続く雨で、旧暦の3月、現代の暦だと3月下旬から4月上旬に降る雨を指すようです。(桜の満開宣言直後に雨が降って、路は散った花びらでいっぱい、なんて毎年みかける光景ですよね。)
さて、、今回ご紹介するワインはこちらです。
≪石橋の飲んでもらいたいワイン紹介≫
銘柄:Harusame / ハルサメ
造り手:Alberto Anguissola / アルベルト アングイッソラ
地域:伊 エミリア=ロマーニャ州
ブドウ:ピノ ネーロ
タイプ:ロゼ・微発泡
希望小売価格(税抜) : 3,400円
ハルサメといえば、澱ごとボトリングされたままリリースするという、ある意味ギャンブルに近いリスクを冒した2014年(いまだ現行…)が皆さまの印象に残っていることかと思いますが、スタッフからすると実験的に少量だけ造られた2013年マグナムこそが、このワイン本来の姿だと思っております。
モストだけで醗酵したワインに、冷凍保存しておいたピノ ネーロのモストを添加してボトリングし瓶内で二次醗酵。当時飲んだ2013年に対する印象ですが、ほんのりベリー系の香りに軽快な酸と泡。難解さを感じさせない端正な味わいは、カゼビアンコに続くヒット商品になるのでは??と予期させるものでした。しかし、その後にリリースされた2014年は世間的には初めて日の目を見るヴィンテージであるにもかかわらず、澱のニュアンスの強い説明書が必要なやんちゃなワインに。
そして、その2014年が長期在庫を続けるなか届いたのが2016年。その2016年を飲んだときに“ああ、この感じ”と、2013年を初めて飲んだときとほとんど同じ印象を受け、非常にほっとした気持ちになったのを覚えています。
2014年が長期在庫を続ける中、当時、新着の2016年を試してみようという方もあまりいなかったのか、動きが全く芳しくありません。2016年はネガティブな要素が見当たらないどころか、春めいた時期に最適な1本と思いますので、是非このタイミングで一度お試しいただきたいと、今回ご紹介するに至った次第です。
そして、このままでは2014年が散々なので、補足を。
そもそも、初めてまとまった量をリリースするタイミングで、なぜ澱ごとボトリングするというリスクを犯したのか??理由は大きく2つだと思います。ひとつは、「スペースとお金」。ふたつ目は、「2014年というヴィンテージ」。
昨年秋、太田のイタリア出張に同行し、アルベルトのセラーを見学させてもらったのですが、(生産量に対し)とにかく狭いんです。。。
タンクや樽を置くスペースに、ところ狭しと機材やリリースを待つボトルが置かれているのがおわかりになるでしょうか?
2014年入荷時の太田が書いた文章にこのような記述がありました。
“アルベルトにデゴルジュマンをしようと考えたことはないのかと聞いたところ、「スパークリングワインとしての特質、美徳をワインに付与するためには、シュールリーの状態で最低でも数年は寝かせるべきだと考えているんだけど、今現在はうちの経済的な事情がそれを許さないわけで…。だったら澱引きせずにリリースして、ワインが成長する余地を残してみようと考えたんだ。置いたら置いただけ変化も望める上に、熟成も緩やかに進むわけだし。」とのことでした。”
類を見ない厳しいヴィンテージだった2014年のブドウのポテンシャルを考えると、シュールリーにできるだけ長い時間が欲しい、だけどそのボトルを置いておくスペースも経済的余裕もない(≒リリースするまではインポーターからの収入もない)。こういった苦しい事情から、2014年を半ば賭けに近い状況でリリースせざるを得なかったのだと思います。
こういったワインは当然彼自身も売るには難しく、生産量の大半が日本に来たというのも想像に難くないです(ダニエーレ ポルティナーリのナンニ2014にも近しいものを感じます)。しかし、こういったワインを買い支え消費してきたことが、造り手のヴィナイオータや日本に対するポジティブなイメージを積み重ねていっているのだと、いちスタッフとして感じます(行き先が見つからなければ商売的にも行き詰ってしまうし、増築する資金を確保できるようになっていかなければ、描いている理想には辿り着けないわけで。。)。
ということで、このハルサメ2014ぐらい「清き1本を!」という言葉があてはまるワインもなかなかないのではないでしょうか?ちなみに、最近の状態ですが、先日抜栓(セルフデコルジュマン)したところ、澱は完全に沈みきっておりクリアな液体へと変貌しておりました。澱由来のニュアンスはまだ若干ありますが、冷やしていただければポジティブな要素が上回ることは間違いないかと思います。
最近の状態(Facebook投稿より)
●セルフデゴルジュマンのやり方はこちら→Click!!
清き1本を!!よろしくお願いいたします。

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・5月その1(Davide Spillare,La Visciola,Vodopivec,Alberto Anguissola(CASE)、De Bartoli,De Fermo,Fonterenza) 
【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2025年2月その4(Gravner,Alberto Anguissola,Il Colle,Pacina,Arpepe) 
【新入荷】2024年9月その3(La Biancara,Cappellano,Alberto Anguissola) 
【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2024年7月その3(Maison Vevey Albert,Possa,La Biancara,Il Cavallino,Alberto Anguissola,Pacina,Le Boncie,De Fermo,La Calabretta,Arianna Occhipinti)