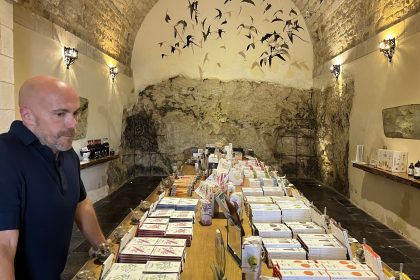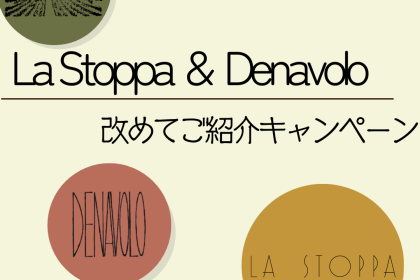ヴィナイオッティマーナ2022【造り手セミナー】ニコリーニ
①セミナー動画 (質問コーナー|03:08~)
ヴィナイオッティマーナ2022 P6 DAY2に行われたセミナーの様子です。今回来日したのはフリウリ ヴェネツィア ジューリアのニコリーニより、当主ジョルジョの長男エウジェーニオ。スロヴェニアとの国境沿いにあるトリエステのムッジャという港町で、代々家族経営でブドウを栽培してワインを生産するかたわら、伝統的な土着品種を、数本だけ残っていたブドウの樹から自分たちで株分けして残しています。
②造り手紹介 (0:00~)
ニコリーニの造り手紹介、詳しくはこちらから。
③造り手への質問と回答
Q1.オスミツァ(農家居酒屋)ってどういうものですか? そして、居酒屋を閉めて自家元詰めに切り替えたのは、どういうきっかけだったのでしょうか?(03:08~)
A1. オスミツァという言葉は、スロヴェニア語でオセムが「8」を意味することから。自分たちが住んでいる場所は元々オーストリアが統治しており、第一次世界大戦前にはオーストリア公国の支配下にあったエリア。文化的にはオーストリアにも「ホイリゲ」のようなローカルワイン居酒屋みたいなものもある。そういうオーストリアのワイン文化の名残りみたいなもの。
オーストリア、いわゆる当時の政府から、ワインを造っている農家が一般のお客さんのために直売してもいいという許可が8日間だけ出た。お酒の場合は酒税もあり厳しく、政府としては税金を取りっぱぐれないように販売を管理していた。だから、「8」という言葉が使われている。そのときに、自分のところで育てた豚で造ったハムやサラミ、チーズ、パンなどでお客さんをもてなしながらワインを飲んでもらう、という文化がオスミツァ。バンドがきて盛り上がるパーティーのような一面もある。
代々そういう感じで最初はやっていて、1980~90年台くらいまでは世間的にもニーズがあったが、以降保健所から厳しく指導が入ったり、若者が夜遅くまで騒いで問題になったり、とちょうどボトリングしたワインのニーズが高まってきたこともあいまって、生産するワインはすべてボトリングする方向に舵を切った。
Q2.伝統的な土着品種を株分けしているということですが、どのようにして行っているのでしょうか?(10:05~)
A2. モスカート ディ イストゥーリアやボルゴーニャというブドウ品種のブドウの苗は、苗屋さんがつくっていない。つまり市場に存在しない。
自分たちの地域は、いわゆる旧ユーゴスラヴィアやオーストリアに元々統治されていた場所で、イタリアになったのはここ100年くらい。その土地の文化に関してはイタリア自身もやや軽視しており、その土地でずっと育てられてきたブドウ品種のいくつかがDOCのリストから外れていることも事実。文化や伝統には理由があると信じているので残すことにしている。
まずは、ブドウが死んでしまった歯抜けの場所から樹を抜いて、アメリカの台木を植える。その台木がある程度育った段階で、たとえば畑に植わっているボルゴーニャの樹の中でも、いいブドウを生らしたり、健康的であったりするブドウの株を剪定したときに枝を取っておいて、アメリカの台木に接ぎ木して増やす、というやり方で毎年小さく続けている。
Q3.グラッパはどのようにして造っているのでしょうか? (14:44~)
A3. アルト アディジェから自分たちのエリアまでオーストリアの統治下にあった当時、オーストリア公国のマリア テレジアが、そのゾーンに住むすべてのワイン生産者に対して、ワインを造ってその搾りかすでグラッパやフルーツブランデーなどを蒸留してもいい、という許可を下ろした。国としては酒税の関係もあり厳しく管理したい部分もあるが、その名残で年間300Lまでは今でもグラッパの製造が許されている。
オーストリアだった時代にその土地に根差したルールのようなものが、イタリアに併合された後も残っている。一般的には、搾りかすを蒸留所に送って、蒸留所が造ったグラッパを造り手が買い戻すのが通例。自分たちの土地では、ワインの造り手であっても自ら蒸留することが許されている。
今はどういう形で機能しているかというと、今年はグラッパを造りたいという旨を税務署に申請すると、72時間だけ蒸留する免許をもらえる。そして72時間寝ずに、三交代制でずっと直火式の蒸留器の火の番をしながら、どんな時間にも税務署の人がルールを守っているか検査しにくることが許されている。合法的にグラッパを造れる権利が残っている歴史的背景がある。
④まとめ
取り扱い歴は長いですが、いままで来日したことがなく情報も決して多くなかったので、個人的には謎に包まれた部分が多かったニコリーニ(エウジェーニオもほとんど外国に出ることはないそうです)。今回のセミナーを経て、いくつかの疑問が晴れました。
人の都合で国が変わったり流行り廃りに振り回されたりしますが、彼らが行っているのは実直に伝統、そして風土を守り紡いでいくということなんだと強く感じました。(担当:石橋)

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2026年2月その1(Two Metre Tall, Shobbrook Wines, Nicolini, Luigi Tecce) 
【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2025年6月その1(Daniele Piccinin(Muni), Nicolini, Ezio Cerruti, Trinchero, Daniele Portinari, Il Censo, Possa) 
【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2025年1月その1(Lasserra,Daniele Portinari,Stefano Legnani,Nicolini,Tropfltalhof,Pacina,De Fermo,Colle Florido,Cristiano Guttarolo,Natalino del Prete,La Calabretta)