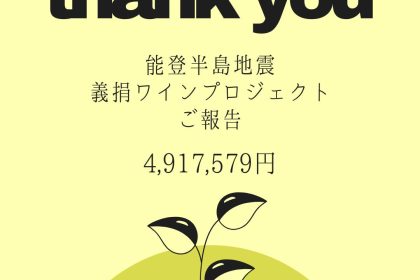おいしさの起源 その1
「おいしさ」というと、その質や範囲、範疇などが人により千差万別な、嗜好性のあるものだという認識が一般的だと思います。
食の好み(何をおいしいと感じるか)は、その瞬間の我々の体調や精神状態、そしてTPO、外的情報などにも影響を受けるものではありますが、その基礎は、生まれ育った場所の文化&社会的背景や家庭環境など、自ら選択する余地のない要素によって形成されるものなのかと。その国、その土地、その家庭独特の食文化や食習慣を端緒として、個々人が持つ好奇心や先入観のあるなし(謙虚さ?)などが触媒的役割を果たしながら、時間と経験を重ねてようやく輪郭を成すものなのだとオータは考えています。
良く 「好みは人それぞれ」とか「~は嗜好品ですから」などと言ったりしますが、オータはこれらの言葉があまり好きではありません。別人同士が感性感覚の世界で完全完璧に同化ないし一致することなどありえませんから、わざわざ言わなくても…と思いますし、会話の中でこれらのフレーズが使われるのは、「私にはあなたの好みが理解できません」をやんわりと言いたい時だけのような気がしまして…。
今現在の“おいしい観”は、偏見や先入観に満ちていた過去のオータの“イケてないおいしい観”を自覚し、恥じ、修正することを積み重ねてできあがったものだと僕は考えています。そして現在の“おいしい観”も、オータ自身が今以上に先入観などから自由になった暁には、嗜好という言葉を越え、より普遍的なものになっていくようなイメージを持っています。嗜好のもっと先に普遍性があるだなんて、イマイチぴんと来ないかもしれませんね(笑)。ですが、個々人の好き好みは、“好ましさ”に具体的なイメージ(理想像)があれば茫洋(形を捉えられないほどに大きい)ではいられませんし、偏見や先入観に囚われていなければ、狭すぎる(排他的な)こともないと思うのです。
ありとあらゆる価値観は、物心ついた時から不変なのではなく、大小さまざまなアップデートを繰り返しながら、よりブレの少ないものになっていくもの(なはず!)。多くのアップデートは、とても微細なものなのですが、その小さなアップデートを長い時間をかけて何度も何度も繰り返していくと、初期設定の時からは想像もできないものへと変容している…。ですが、そのアップデートがあまりにも微細かつ断続的なため、当の本人は自身の価値観が当初のものからはドラスティックに変化したことに気付けていない…。
と、ここまでは小難しく書いちゃいましたが、ここからはオータやオータの身近な人が、それまでの狭小なおいしい観を痛感することになったエピソードをいくつかご紹介しますね。
ブロッコリー&カリフラワー:平成生まれの方たちには想像もつかない話だと思いますが、オータが幼かった頃にはそれほどポピュラーな野菜ではありませんでした(少なくともオータ家では…)。野菜嫌い(だと思い込んでいた)の母親のせいもあり、オータ家の食卓には並ぶことなく18年間過ごしてきました。大学1年の夏休みにニュージーランドで約1か月ホームステイすることになったのですが、そのホームステイ先で用意してくれるディナーのメインディッシュにはいつもブロッコリーないしカリフラワーが副菜として添えられていて…。残すものなんだし…と思い、意を決して食べてみたところ、全然普通においしい…。帰国後、母親に「普通においしいものを、おいしくないと思わせやがって!」と詰め寄り、料理して食べさせてあげたら「あら本当ね。」と母(笑)。母の野菜嫌いは、僕が正したと言っても過言でない気がしております…。
納豆などでは良くある話な気がしますが、両親の食わず嫌い(ないし、自身の文化になかったものに対する偏見)が、子供にナチュラルに受け継がれているケース。
ピーマン:中学2年生くらいまで、ピーマンは苦いだけで全くおいしいものではないと思っていたのですが、クラスメイトのお弁当に入っていたピーマンの炒めものを食べてビックリ。しっかり炒めてあったため、苦みや青臭さが少なく、甘みさえ感じる…。醤油の焼けた風味がピーマンの苦みを更に後ろの方に追いやってくれていて、苦いのが苦手という、実にお子ちゃまな味覚だった当時のオータには非常に心地良く…。
おいしくないと思っていた食材も、料理の仕方次第ではおいしくいただけることを知った14歳のオータ…。またしても母親のせい(笑)。
ビール:苦いばっかりで他の人たちがおいしいと言う気持ちが全く理解できなかったビールを、初めておいしく感じた瞬間のことをオータは鮮明に覚えています。
おいしいと感じた瞬間のオータとその一瞬前のオータとでは、2つの全く異なるおいしい観を持ち合わせていることに…。
バームクーヘン:オータにとっては、自然同様に畏怖の対象であるオータ妻(笑)と、約20年前のとある日にバームクーヘンの話になりました。彼女が「全然おいしいものじゃない。こんなお菓子なくなっちゃえばいいのに。」的な事を言ったと思うのですが、それに対して「確かに俺もバームクーヘンってすっごいおいしい!って思ったことは一度もない。でもそれって、たまたまおいしいのに出合えてないだけなんじゃない?昔から現代までずっと作り続けられたことに、何らかの理由があるんじゃないのかな。」と答えたのですが、その数日後においしいバームクーヘンに遭遇してしまう僕たち(笑)。
時代を超えて、連綿と受け継がれてきたものに悪いものなどあるはずもなく、問題はどちらかというと、ちゃんとしたものに出合えているか否かというところに…。
固定概念や先入観に縛られていることを自覚し、そこから少しでも自由であることを志向し、身体の声に耳を傾けられるだけの分別がつくようになった時には、我々のおいしい観は概ね重なったものになるのでしょう。そしてほぼ重なっているのなら、嗜好という言葉の使用頻度は圧倒的に減ると思いますし、その結果嗜好という言葉自体の重みも増すことになるのではないでしょうか。
いつものごとく、タイトルに掲げた“起源”にさえ辿り着けませんでした…。長くなってきたので、続きは次回ということで…。