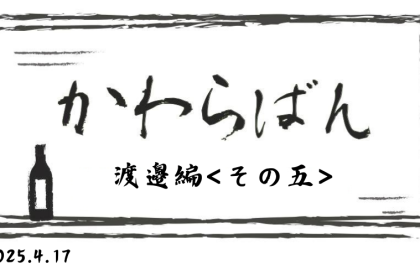おいしさの起源 その4
欧米諸国と比べたら、1人当たりの消費量など全然大したことありませんし(イタリアやフランスの1/15程度)、最大のワイン消費国であるアメリカの約1/10の消費量しかない日本ですが、ナチュラルワインにとっては世界最大の市場といっても過言ではないと思います。イタリアの造り手やワイン関係者から、日本でなぜナチュラルワインがこれほどまでに愛されているのかという質問を受けることがあるのですが、オータは、我々日本人が持つ美意識や精神性、自然観などと、ナチュラルワインの基本理念との間に、高い親和性があることが要因なのでは?と答えています。どういう事かといいますと…
“侘び寂び”という言葉に代表されるように、強くインパクトのあるものだけでなく、淡くはかないものさえも美と捉える感覚が、我々日本人にはほぼ無意識レベルで備わっています。ヨーロッパと比べると、日本の水は柔らかく(軟水)、野菜の味わいも繊細。そして調理面でも、油分を駆使しない料理のほうが少ないヨーロッパに比べ、伝統的には揚げる以外の形で油を使用してこなかった日本の料理は、総じて軽い仕上がりになるといえると思います。そういった背景があるからか、日本では淡い味わいのことも、“はんなり”ですとか“淡麗”というような言葉で、美しいものとして表現してきたのかと。
地震、津波、台風、洪水、土砂崩れ、火山噴火…ありとあらゆる災害に事欠かない日本。自然の猛威とその猛威に対するヒトの無力さを、日常的にとは言わないまでも、かなりの頻度で思い知らされてきた我々の中には、無常観ですとか諦観の念といった精神が宿っています。災害は、誰にとっても喜ばしくもなんともないイベントではあるのですが、それも自然が見せる表情の一端であり、自然の中で生きている(ないし、ヒトも自然の一部である)限り完全に避けることもできないもの。ヒトがあらゆる予防策を講じたとしても、災害の猛威がそれを凌駕し、甚大な被害が出てしまう事も多々あります。これほどまでに文明や科学技術が進歩を遂げた今現在でも防ぐことができないのですから、昔の人たちは災害の度に、我々以上の無力感と自然への畏怖の念を感じていたのではとオータは想像しています。そういった風土だったからこそ、自然物や自然現象などを神格化する神道という宗教が日本に生まれたのではないでしょうか。
に対して、職業柄大地との直接的なコンタクトが必須な農に携わる人たちは、災害の種類、規模の大小、頻度の差こそあれど、自然の猛威を身をもって体験しているでしょうから、人種、国籍、宗教観などの違いに関わらず、我々が言うところの諦観の念を持ち合わせているはず。自然に予定調和などは存在せず、“良い天気”と“悪い天気”という認識も、あくまでも我々の都合からすると…という話でしかありません。ヒトも自然も、表裏ないし陰陽があるものですし、一見ポジティブな事も、違った場面ではネガティブにもなり得、そしてその逆もまた然りなケースも…。太陽がなければ、作物は育ちませんが、全く雨が降らないのも都合が悪く、多雨は作物の健全な生長を阻む可能性もありますが、場合によっては“恵みの雨”などと呼ぶこともあり…。ヒトの場合だと、一徹とか一途などと表現すると聞こえは良いですが、頑固とか意固地と表現すれば悪くも聞こえ…。
“自然のあるがままを受け入れる”というのは、自然からポジティブな贈り物(だけ)を受け取ることを期待しつつも、時々ネガティブなものも勝手に配達されちゃうことがあることを覚悟することとも言い換えられるかもしれません。この“自然のあるがままを受け入れる”というフレーズが、“ヒトがヒトを愛する”というのと似ているなぁと思うのは、オータが美徳よりも欠点のほうが多いと自認しているからなのでしょうか(笑)。
ナチュラルワインを志向する造り手であるのならば、何らかの招かれざる気象イベントの結果として、健全&高品質とはいえないブドウしか収穫できなかったとしても、痩せたブドウを無理矢理リッチにするような人為的な“補正”という手段に頼ることなく、その年のブドウのあるがままを表現すべくワインを仕込むはず。
1年を通して雨が多かった年には、線の細いワインができあがるわけですが、諦観の念を標準装備する我々日本人は“それが自然(普通)”と思える上に、はかないものにも美を見出す気質も持ち合わせています。そして、日本独特のテロワールとそのテロワールで育まれた食文化の影響もあり、淡い味わいも美味と捉えて愛でてきました。
そんな要素が、日本でのナチュラルワインの愛飲ぶりを後押ししてくれているのではとオータは考えています。
スタンコ ラディコンが、生前こんなことを言っていました。
「太陽が欲しい時にしっかり照ってくれて、雨が欲しい時に適度に降って、雨の後にはいい感じの風が吹いてくれたりと、シーズンの始まりから収穫まで素晴らしい天候に恵まれる年がごくごくたまにある。そういう年は、ブドウ樹も一切ストレスを感じることなく生長するからなのか、完璧としか言いようがないブドウができるんだけど、ぶっちゃけそんなブドウでだったら、誰でもうまいワインなんて造れると思うんだ。でもその逆に、(厳しい天候に祟られ)きっついブドウしか生らなかった時に、ちゃんとうまいワインができたとしたら、それは俺たち造り手の手腕の賜物ってことなのかと。当然のことながら、完璧なブドウで造ったワインのようなテンションには欠けるかもしれないけど、収穫の時もセラーでも滅茶苦茶手を煩わされる分、思い入れも強くなっちゃうもんでね…。ま、馬鹿な子ほど可愛いってやつかな(笑)。」
スタンコが“手腕”と呼んだものは、技術的な部分だけを指しているわけではありません。房全体が完璧な状態のブドウの場合、枝から切り離すためにハサミを一回入れるだけで収穫完了となりますが、房に腐敗果等が散見する場合、枝から切り離した後も何回もハサミを入れて腐敗果を取り除き、健全な粒だけを房に残すようにしなければなりません。スタンコのように酸化防止剤を添加せずに醗酵を行う造り手にとって、ブドウの品質が厳しい年には選果は必須なわけですが、選果には膨大な時間がかかる上に、選果すればするほど収量(=生産量=収入…)も落ちるという三重苦が待っていたりもします。
スタンコがいうところの手腕とは、経験、知識、知恵とそれらを基礎にして築き上げた技術、信念、情熱、我慢強さ、自然への敬意と諦観の念、そして諦観しつつもその年の個性(美)を尊重し、その年のブドウなりの最良を実現しようとする不屈の精神など、様々な要素が融合したものの事を指しているのかと。
テロワールの美、ブドウの美、その年の美と、これら3つの美を最良の形で液体の中に表出させるべく、ある時には指揮者、またある時にはプロデューサー、はたまたある時にはミキサー的な役割を担う造り手の“手腕の美”が色濃く反映しているものであるのなら、尊大、リッチ、余韻が長い等々はさておき、とりあえず美味しいワインと呼んでも差し支えないとオータは思うのです。
つづく(また終わらなかった…)