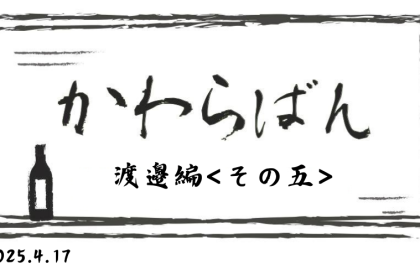おいしさの起源 その3
カーゼ コリーニのロレンツォ博士とオータとの間で、もはやお約束ネタとなってしまった感のある掛け合いがあります。どんなものかと言いますと…
“(ロレンツォのワインを飲んで…)オータ「うん、おいしい(Buonoブオーノ)!」
ロレンツォ「気に入ってくれたのなら嬉しいよ。でも、(私の)ワインがおいしい(ブオーノ)かどうかは、私にとって、さして重要なことではない。ヴィンテージ(の個性)が感じられるものであったのならば、それで十分。」
オータ「いやだから、俺が使うブオーノって言葉の中には、そういった事も含まれているんだってば!」”
彼と知り合って14年ほどになりますが、これまでに何度この掛け合いをしてきた事か…。
何年もかけて互いに言葉を重ねてきましたので、ロレンツォはオータが意図するところの“ブオーノ”が指すものが何なのかをちゃんと分かっているのに、オータをからかいたくてそう言っているだけなのですが…。
“(私の)ワインがおいしいかどうかは、私にとって、さして重要なことではない…”
この一節を読んで、「あれ?どこかで聞いたことあるような…。」と思った人もいらっしゃるのでは?そう、オータが敬愛する石川達也杜氏が、世間をざわつかせるため(笑)に使っていたフレーズです。こういった発言に対して、「自身が醸した酒(ワイン)が、おいしくなくても良いってこと?」と曲解する方も時々いらっしゃるようですが、彼らの真意は少し別のところにあります。
石川杜氏の場合、“おいしさ”の定義そのものが人によってまちまちであり、仮においしさにある種の形(流行りの味筋など…)があったとしても、彼自身それを狙うことを良しとせず、自身のエゴや都合を極限まで排して、“自然の流れ”のようなものを意識した酒造りを理想としているため、そういった信条が結実したものとして生まれた彼のお酒が“好まれない”(おいしいと思われない)可能性もあることを認めている(受け入れている?)…というのが真意の一端なのだとオータは理解しています。
杜氏は、酒とは人が狙って“作る”ものなのではなく、あくまでも“造る”(=神への祈りとともに育てる)ものであり、自然からの授かりものなのだと言います。授かりものだと認識できたのなら、授かったことだけでありがたいと思えるのでしょうし、良し悪しや優劣といった考えは持ち込まないはず。各種能力や性格には大きな隔たり(優劣?)があるオータの3人の子供たちも、オータにとっては各々がかけがいのない存在で、生まれてきてくれて、元気に育ってくれているだけで、すごいありがたいと思える…ワインも日本酒もそれらを醸している人たちにしてみれば、子供のような存在なわけです。
更に杜氏は、彼の考える“いい酒”の条件を、「生きる力(ないし、生きたいという意欲)を湧きあがらせるもの」や「関係性を呼ぶもの」と定義しています。
とあるお酒を飲んで、なんだか無性にお腹が減ってきた…といった感じになったとします。“食べる=生きる”ですので、食欲に火をつけたのなら、生きたいという気持ちに火をつけたのと同義。
ヒトは1人では生きていけない動物ですから、とあるお酒を飲んで人と話したくなったり、会いたくなったとしたら、社会と交わりたいと思ったのと一緒。意識するしないにかかわらず、社会的であること(社会性を備えること、社会の一員であること)は、我々が生きていくためには絶対に必要なものなはず…。
話をロレンツォに戻します。ほぼ同様のワイン観を持っているはずのロレンツォとオータなのに、互いが使う“ブオーノ”の意味合いが少々違う…。ロレンツォが使うブオーノは、彼自身がその感覚に与しないまでも、彼の周りで一般的に使われている(認識されている)ものなのに対して、オータの“ブオーノ”は、オータ自身で積み上げたり、磨き上げたりしてきた感覚なのですが、外的環境(文化や与えられた状況など)にも影響を受けて形成されたものである時点で、オータと似たような“ブオーノ”に行きついている人は、他にも何人もいるはず。つまり、オータのブオーノは、考え抜いたうえでできあがったものではあるのですが、それほど異形なものではなく、普遍性といいますか一般性があるという事に…。この違いが何なのか、ずっと引っかかっていたのですが、とある日閃いちゃったんです!ロレンツォのブオーノは、“良い味”とでも訳すべきなのに対し、オータのブオーノは“美味”を指しているのだと…。
ヒトが食べ物に求めてきたものは、安全性、栄養価の高さと消化吸収のしやすさだと折ある毎に触れてきましたが、各種栄養素の中でも糖質や脂質といった“生”に直結する栄養素に関しては、豊富に含まれていればいるほど都合が良かったわけです。そのような、DNAレベルで刻み込まれた“豊富”に対する憧憬を発端に、ヒトは味わいのリッチなものを、良い味と捉えるようになっていったのかと。
ワインの場合、凝縮感のある完熟ブドウが味わいのリッチさや芳醇な香りをもたらし、そしてそのようなブドウを収穫するためには、1年を通して天候に恵まれる必要があります。この理屈ですと、ロレンツォが言うところの“おいしい”ワインは、天候に恵まれた“良い年”のブドウから(だけ)造られるということに…。
それに対してオータのブオーノは、美しい味と書いて美味…。拙コラム“美の起源”(https://vinaiota.com/blog/otablog/4843)の中で、
“「美」とはヒトの力、理解、想像、予想を遥かに超えた圧倒的な存在に対して抱いた畏怖の念を端緒にしていると考えています。そしてその“圧倒的な存在”とは、我々に大いなる恵みも、甚大な災いをももたらす“自然”であることは言うまでもない事かと。
ミクロそしてマクロ、そのどちらの世界においても自然が見せる表情は実に様々。繊細なものもあれば暴力的なまでに力強いものも、淡い色もあればヴィヴィッドな色も、悠久もあれば刹那も、精緻の極みとも言える幾何学的な模様もあれば捉えどころのない“ゆらぎ”のあるものも…。
“美”とはつまり、自然界の中にあるありとあらゆる事象が、その場所その瞬間にしか表現し得ない唯一無二性を表す概念として生まれたものであり、「~は、~より美しい」というような、優位性を示すものではないとオータは考えます。”
と書きました。
では、ワインが表現しなければいけない美は何かといえば、
1.その地域、畑、区画だけが持つテロワール特性
2.ブドウ品種の個性
3.ヴィンテージの独自性(その年に起こった一連の気象的イベント。場合によっては、それ以前に起こったイベントの余波さえも…)
1年を通して雨が多かったヴィンテージのワインは、天候に恵まれた年のワインと比べると、味わい的に線の細いものになるわけですが、この線の細さこそが、そのワインが表現すべき“美”なのでは?
4.そのテロワール、そのブドウ、そのヴィンテージが持つ個性(美)をワインに反映させるために、各々の造り手が示す良心の形(我の殺し方とも言えるかもしれません)
の4点に集約するとオータは考えています。
4に関して、少々補足します。1~3までの自然美が、ワインという液体の中に余すことなく表現されている事を願う(理想とする?)造り手ならば、農業と醸造のどちらの場面においても、“できるだけ~しない”や“~しない”という非干渉主義的な選択が増えるはず(“全く何もしない”という事ではありません!)。
とはいえ、ナチュラルワインを志向する造り手たちの中でも、大切にしている信条や理念のありかたは、人それぞれ。自らの置かれている状況の中で最大限の“~しない”を実現しようとしている点は皆一緒であっても、課しているハードルの質や高さには差や違いがあり、“より攻めている”造り手だけが正しいというわけでもないとオータは考えておりますので、“良心の形”と少々曖昧な書きかたをしました。
皆さんにも想像していただきやすい例をいくつか挙げますね。
ボルドー液という、有機農法でも使用が認められている、硫酸銅と消石灰を成分とした農薬があります。使用が認められている農薬であったとしても、銅という重金属を含有するため、多くの造り手は使用量を極限まで減らそうと努力しているのですが、造り手によっては(銅という重金属を畑に撒かないために、ボルドー液を)一切使用せず、天然成分由来の代替品を使用するケースも…。
醸造面でいうと、酸化防止剤の使用うんぬんが上記ボルドー液の話と似ているかもしれません。“できるだけ使用しない”というポイントに関しては、全ての造り手が思いを同じくしているのですが、完全無添加を良しとする造り手もいれば、基本無添加だけど必要と判断した時には少量添加する造り手もいますし、飲まれるまでの保管状態が万全でない可能性を考慮して最低限の量は必ず添加するという造り手も…。
グラヴネルやヴォドピーヴェッツのような徹頭徹尾な人ですと、セラーでの過剰な電力使用もナチュラルワインというコンセプトから逸脱すると考え、セラー内の空調も認めず(人為的な温度調整にあたると考えているため)、醗酵&熟成容器にも土(アンフォラ)と木(樽)という天然由来のものだけを(両ワイナリーともステンレスタンクを1つも持っていません!)。そして、ボトリング時も無漂白の天然のコルク栓(彼らが使っている最上級のものになると、1本1ユーロ以上するんです!ひええええ!!)のみを使用…。
各々の造り手が彼らの良心に従って導き出した答えに差こそあれど、不正解は存在しないのでは?といった結論にオータは数多くの造り手と交流する中で至っています…。
つづく(この回で終わらせるつもりだったのに…涙)