造り手紹介 ヴォドピーヴェッツ その2-序章(2014.10筆)
2011年のヴィナイオッティマーナを境に、日本のワインマーケット内での認識や立ち位置が劇的に変わった造り手は?と聞かれたら、迷わず“2014緑”11月来日のヴォドピーヴェッツと“2015赤”2月来日のラディコン(あ、書いちゃった!笑)と答えるでしょう。
オッティマーナ以前も、テロワール、ヴィンテージ、ブドウ品種、そして造り手自身の個性を強く反映した、“攻めた”造り手という認識が世間的にもあったと思うのですが、肝心のワインの味わいに対する認識が、“きっと凄いんだろうな…”的な、体でというよりも頭で理解を完結させてしまっている、つまり、それほど量を(←ここ大事です)飲まれることなく形成されてしまったものだったような気がするのです。
価格も決して安いわけではないので、おいそれと開けることなんてできないよ!と言われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、その価格での尻込み具合(笑)以上に飲まれていなかったとも思っています。
それに対して、今現在は彼らのワインがごくごく普通に、そこかしこでごくごく(笑)飲まれているのを実感できるんです。この“飲まれている感”は、“売れている感”とは全く別物だという事も念頭に置いてください。
なぜそうなったのか?
真相は僕にも分かりません(笑)。
ですが、僕自身に関してだけ言えば、ある程度の答えが出ています。
恥を忍んで告白しますが、誰よりもヴォドピーヴェッツ&ラディコンを信じていた僕でさえ、3-4年前はプライベートで開けることが月1-2回程度だったんです。それが今では、ことある毎に彼らのワインを開けて、ごくごく飲んでいますし、その頻度たるや他の造り手のワインを軽く凌駕していると思います。
なぜか?
理由1:家(つまり地下倉庫)にいっぱいあったから(笑)。
理由2:理屈抜き(←大事です)で美味しくて、ザクザク飲み進んで、飲み飽きしなくて、どんなお料理とも渡り合えるから。
理由3:ヴォドピーヴェッツもラディコンも複数ヴィンテージが長年に渡って在庫として存在していたため、定点観測がしやすい状況だった。繰り返し飲んでいくにつれ、凄いとは思うけど若干尊大で、取っ付きにくいキャラなのかと思っていた奴(ワイン)が、実際は案外気さくな奴だった、ないし時間が彼自身を成長させ、気さくになったか、もしくは長い時間を共に過ごすことで、こちら側の彼への理解・見識・認識が深まったとか…。知りに行けばいくほど、新たな発見があり、もっと新たな発見があるのでは?と思い、また開け…というメビウスの輪にはまり、それと同時に理由2にも行き当たり…。
何が言いたかったのかよく分からなくなってきましたが、色々な偶然必然がタイミング的に重なり、僕同様に理由3の罠にはまった(笑)人が続出し、現在のような状況になったのかなぁと。
ここ2年くらい、公私に渡って仲良くしていただいている竹鶴酒造の石川杜氏は、彼の考える“良い酒”を、“関係性を呼ぶもの”と定義しています。
食べ物を呼ぶ(食べたくなる)という事は、生きる糧を求めるという欲、つまり生きたいという欲する気持ちが湧くという事。
人を呼ぶというのは、一人では生きていけない、社会性を重んじる動物である人間が、他者との繋がりを欲し、共に生きていきたいと思う事。
飲んだら食べたくなり、食べたら飲みたくなる、とか、飲んだらなんだか人と話したくなる…そんな酒こそ理想なのではないか、それはある意味“美味しい”こと以上に大切なことなのでは?というのが石川さんのメッセージという事になると思います。
石川さんは、「極端な話、酒自体の味は不味くてもいい」とまで言い切り、僕は僕で、「ワイン(お酒)にとって最も大切なのは、クオリティではなく個性だ」などとうそぶいたりしていると、「え、ヴィナイオータのワイン(ないし石川さんが醸した竹鶴のお酒)は、関係は呼ぶかもしれないし、個性的かもしれないけど、美味しくないものもあるってことなの??」と曲解されるかたもいらっしゃるようですが、そういうことではありません(笑)。
望むらくは、“美味”という一時的な快楽だけでなく、僕たちの身体、精神、感性感覚に“+α”をもたらすものも備わっていてほしい。感心ではなく、心や身体が衝き動かされるようなもの(それを感動とか、本能に訴えかける、とか言うのかと…)が宿っているモノであってほしい。
これはお酒に限らず、食べ物であれ、音楽であれ、なんであれ、僕たちが大切にしている事なんだと思います。こういった次元の話の中に、“クオリティの善し悪し”という観念があまりフィットしない気がするのです。
どんな世界でも、“偉大なもの”は常に尊大だったり、難解であると思われているような気がするのですが、果たしてそうなのでしょうか?
“偉ぶらない偉大”も存在するのではないでしょうか??
ワインは読み物ではなく飲み物であるという自明の事、ワイン(お酒)を頭だけではなく身体全体で感じながら飲める人が増えてきたことが、今現在のヴォドピーヴェッツ&ラディコンのワインの爆発的な飲まれ方に繋がっているような気がします。
ヴォドピーヴェッツの紹介文その2を書くつもりが、思いっきり脱線してしまいました(笑)。ですので、本記事はその2-序章とさせていただきまして、次回記事が、その2となります!!
あ、石川さんと竹鶴のお酒に関しても、お話ししたいことがてんこ盛りですので、また後日書こうと思います!!!
本文とは全く関係ありませんが、2013年春訪問時の昼食

野生のアスパラとパオロのヴィトフスカ、悶絶級です!!!!

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・5月その1(Davide Spillare,La Visciola,Vodopivec,Alberto Anguissola(CASE)、De Bartoli,De Fermo,Fonterenza) 
【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2024年7月その1(Ezio Cerruti,Possa,Bressan,Pierpaolo Pecorari,Natalino del Prete,Arianna Occhipinti,Vodopivec,Borgatta) 
【2024義捐ワインプロジェクト 第一弾】 
【新入荷】オータのアツアツ新入荷&2024年3月その2(Laserra,Vodopivec,Mlecnik,Il Cavallino,Pacina,De Fermo,Cantina del Barone,Cantina de’ll Angelo,Il Cancelliere) 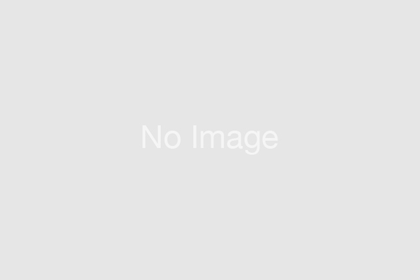
動画配信キャンペーン(ARPEPE, Vodopivec, De Bartoli)







