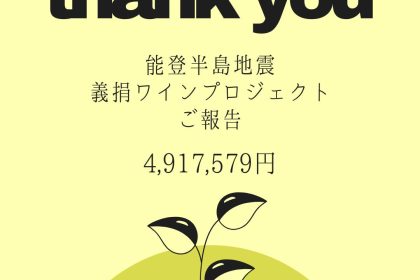造り手紹介 ドメーヌ デ ミロワール
ジャンジャン記事を上げていきたいところですが、過去の資料を整理して、各造り手毎にまとめたファイルを作成するだけでも2-3時間かかってしまいました…。
お次は、鏡健二郎&真由美さんのワイナリー、ドメーヌ デ ミロワールの紹介に行きたいと思います!!
先日再アップした記事は、2年前、彼らの初荷が届く時に鏡氏に書いてもらった、不器用にして実直な文章(まさに彼そのもの!)になります。で、僕はここで、僕と鏡氏の馴れ初め(笑)の話でも書こうかと思います。
話は一旦飛びます。
ご存知の方も多いかもしれませんが、最も僕の琴線に触れるワインを造るフランスの造り手といえばアルザスのシュレールでして、12年前にリースリング キュベ パルティキュリエール2000を初めて飲んだ時の衝撃は一生忘れないと思います。
ここからが凄いのですが、シュレールのワインを知るようになって数か月後、2003年のヴィニータリーの時期のとある日、ラ ビアンカーラのアンジョリーノが自宅に友人生産者を招いてピッツァパーティーをやると言うので、帰って(この時期は毎年アンジョリーノの家に泊まらせてもらっていました)みると、知らない生産者が1人…それがブルーノ シュレールでした。そこにいた事にもびっくりしましたが、イタリア語がペラペラなことに更にびっくり、なんと奥様がイタリア人だったのです!
「あー、お前がシュレールか!日本で飲んだけど、ムッチャクチャ美味しいよね!」と気軽に話しかけられる嬉しさたるや…。
アンジョリーノ、マッサ ヴェッキア、ラディコン、ラ カステッラーダ、ムレチニック、ベア、フランクやダーリオ(プリンチッチ)とシュレールのレアキュベを一緒に飲んだっけ…みんな仲良かったな…ほんといい時代でした…(涙)。
その2年後の同じ時期、シュレールと一緒にいたのが彼のもとで働き始めたばかりの鏡氏で、同い年という事もあり、以降仲良くさせてもらっていました。
気遣い屋で非常に謙虚な男なのですが、凄く熱いモノを秘めていたりします。
シュレールのところで長く働いた彼が、いつ、どこで自分のワインを造り始めるかは、業界内で話題の的だったように思うのですが、彼はその状況を冷静に眺めているように僕には見えました。
それは、「シュレールで長らく働いていた日本人が自らワインを!」とか「日本人がフランスで頑張ってワインを造っている!!」などという同胞愛から来る色眼鏡を拒否し、「俺は俺、ワインの中身で判断してもらって結構!」と言っているかのようで…。
実際、彼がワインを造り始める前から取引を依頼していたインポーターもいたようなのですが、飲んだこともないワインを買おうとするのは、造り手に対してもお客様に対しても失礼なのでは?と僕は思っていました。鏡氏の人となり、自然観、ワイン観を知っていて、彼なら素晴らしいワインを造るに違いないと思っていたとしても、です。
造り手、鏡健二郎への最低限の礼儀として、「日本人であることも、シュレールで長く働いていたことも、いち友人であるという事もとりあえずはどうでもいいわ!まずはワインを飲んでからだぁ!」と鏡氏に豪語し、それを自分への戒めともしていたヴィナイオータが最終的に彼のワインを扱わせてもらえることになりました。
イタリアワイン専門のインポーターだと思われていた感のあるヴィナイオータですが、僕自身にそういったこだわりはなく、ただ単にイタリア語しか話せないから今のような状況になっただけで、フランス語やスペイン語も話せていたのなら、フランスやスペインにも足を伸ばしていたかも…。
僕にとっては、感じたことを自分の言葉で直接造り手に伝えられることと、造り手の言葉を他者(通訳)を介さずに聞くことは非常に大事なことで、イタリア語(と日本語!)しかある程度満足に自分を表現する言葉を知らないので、イタリアだけを周っていて、やってもやってもまだまだ面白い造り手いるんだなぁなどと思いつつ過ごしていたら今になってしまった…その程度の理由なんです。もともと、ざっくりとした線引き、境の設定、カテゴライズに興味も重要性も全く感じていません。
僕の仕事に関わる話で言うなら、イタリアのワインであるとか、ビオとか、オレンジワインとか、アンフォラを使ったワインとか…確かにその言葉自体に間違いではないのですが、全てのイタリアワイン、ビオワインないしアンフォラを使っているワインを手放しで認めているわけではないですし、白(?)ワインがオレンジ色していて、なおかつ濁っていたりしただけで「もう堪らん!」とはなりませんし…。
僕が上原ひろみちゃんが大好きなんですと言えば、「ああ、ジャズが好きなんですね!」とリアクションが返ってくるのも同じようなことかと。即興演奏に醍醐味があるという点が人生にも通じるところがあり、ジャズのコンセプトには非常に共感を覚えますが、別に根っからのジャズファンというわけでもなく、あくまでも上原ひろみというアーティストの音楽が好きなだけで…。
国籍、その人が信じる宗教、学歴、育ちが、とある人の人間性を判断する参考資料にさえならないのと一緒で、生産地(国)、ブドウ品種、ヴィンテージやビオかビオじゃないか等という情報だけで、とあるワインを僕たちが前もって設けているカテゴリーに分類してしまうことは、本当に危険な事なのではないでしょうか?
僕が造り手と直接コミュニケーションをとることにこだわるのは、それがその人を知るための最も有効な方法の1つだからで、真っ当な人間性、考え(ワインの場合、自然観などはその人の造るワインを想像する上で最も重要な情報かもしれません)を持っていると判断できた暁には、自ずとワイン(クオリティ、個性、潜在性、造り手自身の将来性…)も付いてくるということを経験から学んだからに他なりません。
鏡氏も、2014年でようやく4ヴィンテージを経験したことになり、2ヴィンテージがすでにリリースされていて、今現在3ヴィンテージ目にあたる2013年ヴィンテージのワインの一部が日本へ向けて船旅の最中です。2011年を除く3ヴィンテージは、収量的に厳しい年が続き、天候的にも非常に難しいヴィンテージでもあったようです。彼のように、始めたばかりの造り手で、買いブドウでワインは仕込まないと決めている造り手としては、確率3/4での低収量というのは非常に痛手だったと思いますし、それが原因で挑戦しきれてない事とかもあるのだと思います。(例えば、収量がある程度あったのなら、一部のワインの樽熟成を長くしてみたり、それこそヴァンジョーヌ的ワインを造ってみたり…)
ヴィンテージを重ねて、彼がやってみたいと思っていることが実践できる状況が整ったら、どんなワインを造るんでしょうね??2011年のワインとか、10年後はどんな味わいなんでしょう??う~ん、いろいろ楽しみ!!
その年の、その造り手のワインは、その年独自の天候気候と、その造り手のその年Ver.の考え、精神状態、置かれている状況とリスクヘッジの設定具合などが織りなす、打ち合わせなしの、2度と同じもののないセッションと考えられば、“良いヴィンテージ”、“悪いヴィンテージ”や“良いワイン”、“悪いワイン”という観念はなくなるのではないでしょうか?もちろん、アーティスト(造り手)を吟味した上での話にはなりますが…。
また何が言いたいのかがよく分からない文章になってしましました(笑)。
前述の今船旅中というワインですが、1/17に入港予定で、今回のイベントにはギリギリ間に合うか?といった状況です…。ひぃぃぃっ! 間に合う事を皆さんも祈っていてください!!!!!!!!!!
あ、福岡の皆さん、2/11に彼らをお連れできなくてすみません!!2年振りの帰国ということで、短い滞在期間で、両家の実家にもちゃんと出向かねばならず…。

枝を針金に結び付けてる健二郎&真由美さん!!