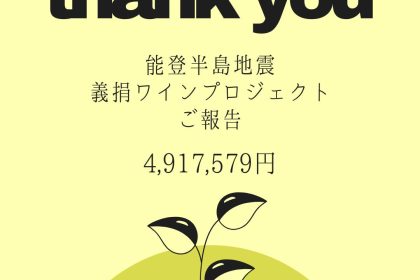【新入荷】2017年4月 その4

先日我が心の師匠、上原ひろみちゃんのコンサートに行ってきました!コンサート自体も最高だったのですが、新たな気付きまでいただけちゃって、オータとても幸せ!!我が師匠、一音入魂をモットーとするだけあって常にキレキレではあるのですが、殊更キレッキレな演奏で聴衆全体の「おおお、すげえぇぇぇぇ」という感嘆&畏怖の念のこもった心の声が重なり合って会場が地鳴りのようなものに包まれる瞬間がコンサート中に2-3回ほどあったりします。そんな時オータの頭の中では、
・演奏そのものが実際に凄い
・その凄さに会場全体が感応していることが現象として凄い
・有無を言わさないだけの説得力のある凄さ、ないしある種の普遍性、共通認識のある凄さの存在が凄い
・聴衆の予想を上回るからこそ凄いと思われるわけで、それを実現表出させた彼女の情熱、想い、そして積み重ねてきたであろう圧倒的な量の修練が凄い
といった数々の凄いが渦巻いていて、特に上記4番目の凄いに想いを馳せた時にオータの目頭は熱くなるのだということを今回ではっきりと認識することができました。
上の4つの“凄い”ですが、演奏の部分をワインに置き換えても非常に腑に落ちるものになると言いますか、オータが理想とするワイン社会像が浮かび上がってく るような気が…。1番目の凄いが4番目の凄いに支えられているものだとちゃんと理解していたのならば、ヒトは他者にもモノにも優しくなれ、安易に良し悪し、優劣という論理を展開しなくなると思うのです。天候に恵まれた年であれ恵まれなかった年であれ、造り手はその時、その瞬間、その場所で出来うる限りのベストを尽くしているわけですから、その年のブドウ&造り手なりのベストの味わいがワインの中にはあるはずなのです(よほどのヒューマンエラーがない限り…にはなりますが)。自然相手の仕事も、その仕事が結実したものであるブドウそしてワインも、1つとして同じものがないというところが最大の魅力なわけですし、差や違いがあるからこそ数ある表現が生まれるのではないでしょうか。
ナチュラルワインを本当に(本質的に)愛しているのならば、痩せた年のワインでさえも愛でられるはずなのですが、消費者の総体としての市場はなかなかそのような反応をしてくれるわけではなく…。“(自然の)恵み”とは、当たり前に享受できるものなのではなくある種の奇跡なのだと認識したうえで色々な年の色々なストーリーの詰まったワインに向き合ってもらえるような世の中…このあたりが、ヴィナイオータが今後情熱をもって取り組んでいくべき課題なのかと!

それでは4月最終週入荷分のご案内行きます!
エミーリア ロマーニャ州でのオータのマネージャー役、アルベルト アングイッソラからいろいろ届きました!オータが彼を訪ねた際、デナーヴォロ&ラ ストッパ(テ ラヴェールさん扱!)のジュリオ アルマーニ、クローチ(相模屋さん扱!!)のマッシミリアーノやアンドレア チェルヴィーニ(モンテ物産さん!!!)のアンドレアなど地域を代表する造り手が各々のワインを持ち寄って宴が催されるのですが、毎回夥しい本数のボトルが開きます(参加者は多い時でも10人弱ですが、30本くらいは開けるのでは?中にはめっちゃ古いワインも…)。その噂が造り手たちの間でも徐々に広まっていまして、次回はステーファノ レニャーニとパーチナのステーファノが参加という話も…。と余談はさておき、今回入ったワインですが…

カゼビアンコ2015:伝統品種であるマルヴァジーア、モスカート、オルトゥルーゴ、マルサンヌを混醸、10日間ほどの醸し醗酵を行った白ワイン。価格の割には香り、味わいどちらの面でもちゃんとパンチの利いたワインです。
カゼ2014:太陽に恵まれなかった年という事で、収穫した大半のピノ ネーロは皮ごと醸すことなく微発泡性ワイン(ハルサメ)となったのですが、通常でしたらリーヴァ デル チリエージョに使われる、樹齢の最も古い区画の斜面上部のピノを使って醸したのがこのカゼ2014になります。

カルカロット2013:この地域の赤の伝統的セパージュであるバルベーラ&ボナルダで造られるスティルの赤。
ベルベック2014:カルカロットと同じ畑で収穫された同じブドウ(バルベーラ&ボナルダ)で造られるワインなのですが、収穫翌春にボトリングし、若干残っている糖分を利用して瓶内2次醗酵を促したワインになります。

リーヴァ デル チリエージョ 2013 lotto 08/2015とlotto 07/2015:リーヴァ デル チリエージョは、アルベルトが一番最初に植えた、そして今現在複数ある中でも最も標高の高い区画のピノを使用しているのですが、この区画の上部に右側(東)と左側(西)で大きく土壌特性が変わるポイントがあります。アルベルト、2013年はその 2区画を別々に醸造してみたのですが、出来上がったワインも個性の面で大きく異なったものになったことから個々にボトリングすることにします。
08/2015は粘土質土壌の区画のもので、アルコール度数的にもちょっと高めで味わい的にもリッチでふくよかな印象のワイン。
に対して07/2015は石灰質土壌の区画で、広さとか大きさよりもミネラル感や余韻の長さに特徴のあるワインとなっています。厄介なことに、両者を識別する術はラベルにも記載されている上記ロット番号のみとなります …。非常にややこしくて申し訳ないのですが、是非とも同時に抜栓し飲み比べていただければと思います!!

シチリアのイル チェンソからはワイン2種とオイルが届きました!!
カタラット ドラートで造られるプラルアールは2014年になりまして、ヴォリューミーな2012とエレガントな2013の中間地点的味わいで、香りは濃密ですが抜群の飲み心地。
ペッリコーネ(ピニャテッロ)で造られるニューロは2013年が届いています。まあまあ渋いですし、濃かったりするのですが、程よく(?)揮発酸があるので飲み心地は全然悪くありません(どんな紹介の仕方なのか…)!どちらも本数的には潤沢に届いておりますので、瞬間消滅はないと思います。ガンガン飲んでくださいね!!
そして初入荷のオイルですが、2015年12月(リグーリアか!ってくらい遅摘みですよね…)に収穫されたシチリアの土着品種ビアンコリッラ、チェラズオーラ、ムルティッダーラを使用したものになります。辛みのない、非常に優しい味わいのオイルです。2016年ではなくて2015年のオイルになりますがご安心ください、賞味期限は2018年5月となっています!!
2016年はシチリア全土的にオリーヴが不作(統計的には80%減だそう…)だったそうで、イル チェンソも先々週に入荷しましたフランク コーネリッセンもオイルのリリース予定はないそうです。こちらも是非!

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・5月その1(Davide Spillare,La Visciola,Vodopivec,Alberto Anguissola(CASE)、De Bartoli,De Fermo,Fonterenza) 
【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2025年2月その4(Gravner,Alberto Anguissola,Il Colle,Pacina,Arpepe) 
【新入荷】2024年9月その3(La Biancara,Cappellano,Alberto Anguissola) 
【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2024年7月その3(Maison Vevey Albert,Possa,La Biancara,Il Cavallino,Alberto Anguissola,Pacina,Le Boncie,De Fermo,La Calabretta,Arianna Occhipinti)