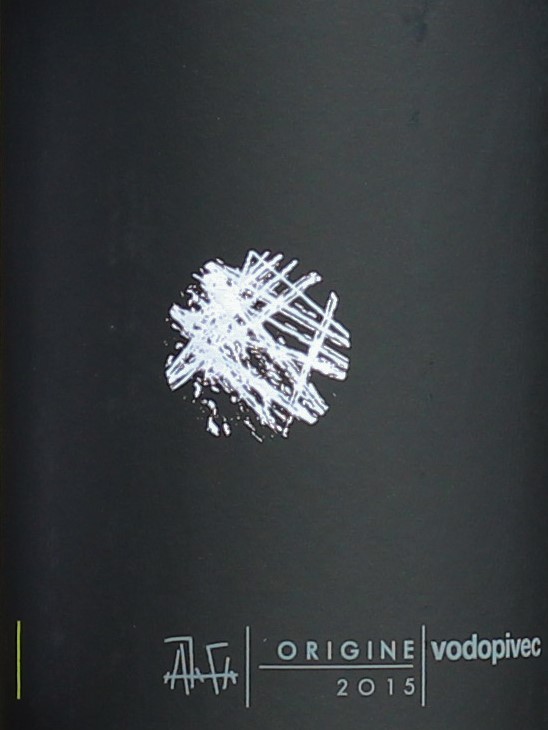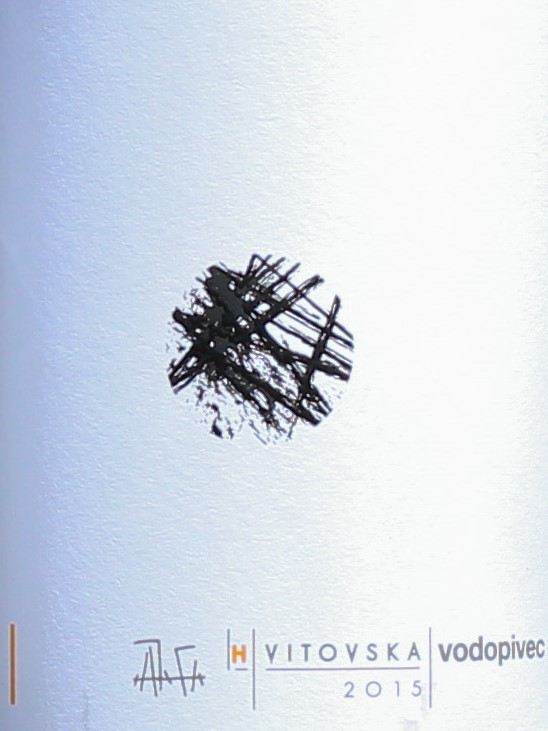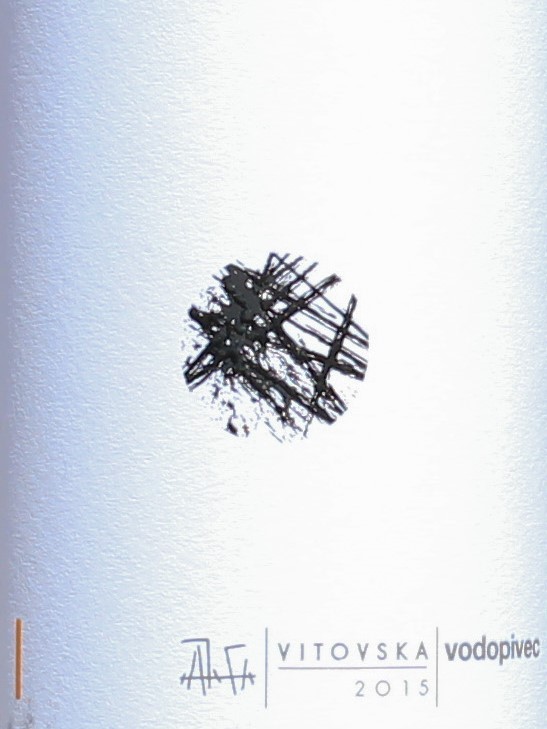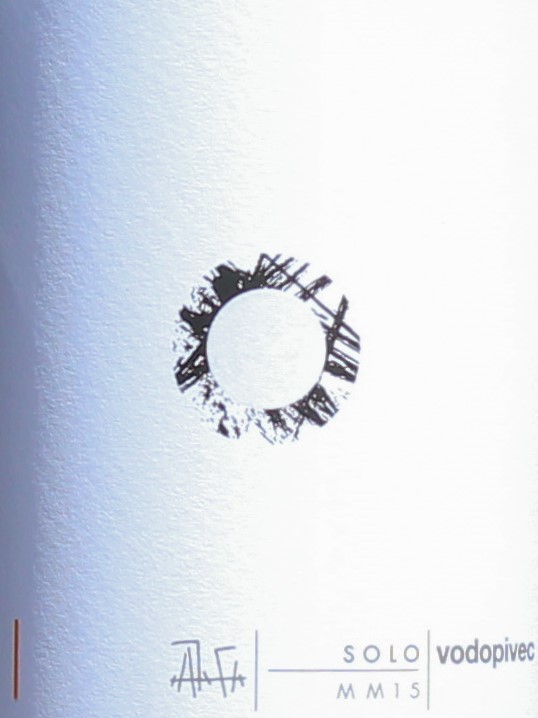造り手紹介 Vodopivec / ヴォドピーヴェッツ
造り手:Vodopivec / ヴォドピーヴェッツ
人:Paolo Vodopivec / パオロ ヴォドピーヴェッツ
産地(州):フリウリ ヴェネツィア ジューリア
ワイン:Origine, Vitovska T, Vitovska H, Vitovska, Solo
所在地:Localita Colludrozza, 4 – 34010 Sgonico TS – Italia <map>
Web:http://www.vodopivec.it/
イタリア北部の東端トリエステから北に15km、カルソ地方と呼ばれる石灰岩の台地のほぼ中央であるズゴーニコ郊外の小さな集落コッルドロッツァにヴォドピーヴェッツのワイナリーはあります。農業学校を卒業したパオロ(当時25歳)は、1994年に弟ヴァルテルと共に起業し、それまで花や野菜、バルクワインの販売で生計を立てていた両親から畑を受け継ぎ、1997年から自家瓶詰めを始めました。
カルソは硬い石灰岩の岩盤で構成されているため土が極端に少なく、一般的にブドウ栽培に適さないと考えられてきましたが、パオロはミネラルが豊富なカルソという土地を表現するにはヴィトフスカこそが最良のブドウであると信じ、100年後にこの場所でブドウを栽培する人たちに向けカルソの持っている可能性を表現したいと考えています。海から10kmほどの場所にある、海抜260mの赤い粘土土壌が特徴的なブドウ畑では、地熱の影響でブドウがより凝縮しつつ、ボーラと呼ばれるこの地域特有の強風に枝を折られないように低めに仕立てたアルベレッロで、ボルドー液以外の農薬は使用せずに栽培を行っています。
収穫されるブドウとの対話の中で決められてきた醸造に関しては、さまざまな試行錯誤の末、アンフォラで醸し醗酵を行い、アンフォラと大樽で熟成を行う現在のスタイルに落ち着いています。2011年に完成した、岩盤をくり抜いて作られたセラーは穴掘り以外の作業はパオロ一人で行われ、大気やエネルギーを均等に循環させるために円を意識した造りで角(かど)がなく、電磁波の影響を受けることなくワインが静かに休める環境を目指して造られました。
<パオロ ヴォドピーヴェッツ インタビュー>
【Full Ver.(1:16:32)】
【Short Ver.(03:15)】
<ワインラインナップ>
●Origine(オリージネ)
品種:ヴィトフスカ
”起源”、”原点”を意味するオリージネは、パオロが初ヴィンテージである1997年から採用してきた手法である、木桶での醸し醗酵を行なったワイン。カルソという地域でも、ヴォドピーヴェッツ家でも、長い間行われてきた醸造方法であり、地域にとっても、パオロにとっても原点と言える。
木製開放式醗酵槽で10~14日間ほど醸し醗酵させた後に圧搾、約3年間大樽で熟成。 1997〜2004年は『Vitovska』、2005〜2006年は『Vitovska Classica』として、2009年からは『Origine』の名前でリリースしている。ラベルの緑の線は、緑→木→木桶を指している。
●Vitovska T(ヴィトフスカ ティー)
品種:ヴィトフスカ
パオロが使っている樽は内側を一切焦がしていないもののため、いわゆる樽香が付くことはないが、それでも樽で熟成させることによって生まれる香りや風味があると言う。ヴィトフスカというブドウ品種の特性をフィーチャーし、よりピュアなヴィトフスカをという想いから、テラコッタという極めてニュートラルなマテリアルでのみ、醗酵から熟成までの全過程を行ったワイン。アンフォラで皮ごとの醸し醗酵と熟成、プレス後再びアンフォラに戻して熟成。TはテラコッタのTからきており、2011年からリリースしている。
2011年ヴィンテージは半年間の醸し醗酵&初期段階の熟成の後に圧搾、2年半の熟成。アンフォラでの熟成は、木樽よりも還元的な環境での熟成のため、タンニンは少し軽くても良いのかも?と考えたパオロ。2012年ヴィンテージは約半量を半年間皮ごと、残り半分を果帽が浮き上がり醗酵が始まったことが確認できた段階で圧搾し、モストを再度アンフォラに戻して醗酵熟成。2013年ヴィンテージは約1年の皮ごと醸し醗酵後に圧搾、熟成させている。
●Vitovska H(ヴィトフスカ アッカ)
品種:ヴィトフスカ
2015年に初めてモストのみで造ったワイン。アンフォラで醗酵、シュールリーの状態で翌年秋まで熟成。澱引きし、再びアンフォラへと戻して18か月熟成。イタリア(語)ではアルファベットのHは、 “無”を指し、果皮がない状態で醗酵させたのでH(アッカ)という名前に。
生まれ育ったコッルドゥロッツァ村で新しく入手した区画で、剪定もされず放置され半野生化したブドウを使用。他の区画のブドウ同様に除梗し、プレスしたブドウをアンフォラに入れていたところ、アンフォラの外にこぼれた一部の果皮が、数時間後には異様なまでに褐変していることに気が付いたパオロ。翌朝には圧搾し、モストだけを別のアンフォラに戻して醗酵。果皮がなかったためなかなか醗酵が進まず、終わったのは翌春で、そのまま澱と触れ合った状態で更に半年熟成させた。2016年秋に澱引きし、再びアンフォラへと戻して熟成させた後にボトリング。
●Vitovska(ヴィトフスカ)
品種:ヴィトフスカ
今現在主流として採用している醸造方法であり、生産量的にも最も多いヴォドピーヴェッツの”ノーマルキュベ”。地中に埋め込んだアンフォラで半年間の皮ごと醸し醗酵と熟成、圧搾した後大樽に移し約2年熟成。ラベルの小さなオレンジ色の線はテラコッタを表現しており、”アンフォラ”の記載がないのは、彼が求める醸造方法を実現するのに必要な熟成容器がアンフォラであっただけで、それをラベルに謳うのはいかがなものか?という彼なりの考えが反映されている。
2005~2009年までは屋外に埋めたアンフォラで醗酵、終了後も皮ごとの状態でふたをし、一冬を外で過ごさせ、翌春に圧搾していた。2010年はベト病蔓延で収量が激減したためこのワインのみの生産となり、初めて現セラーでアンフォラでの半年の醸し醗酵&初期熟成、圧搾後にまた再度アンフォラに戻して半年熟成という過程を行った。
●Solo(ソーロ)
品種:ヴィトフスカ
パオロの”グランクリュ”で造られたワイン。本来だったらブドウ栽培には向かないとされる、15~20cmと極めて薄い表土の直下にある、固い石灰岩の岩盤を自ら砕いて表土を戻して開墾した区画のヴィトフスカ単一でボトリング。単一畑という事でソーロ(唯一の)であり、初めてボトリングを行った2007年に弟ヴァルテルがワイナリーから抜け、パオロ一人になったという事でソーロ(ひとりの、孤立した、孤独な…)という意味も含まれている。
醸造方法はヴィトフスカと同じで、半年間アンフォラで醸し醗酵と熟成、大樽に移し約2年熟成。2004年ヴィンテージを初めて単一でボトリングし、2009年、2011~2016年と生産している。

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・5月その1(Davide Spillare,La Visciola,Vodopivec,Alberto Anguissola(CASE)、De Bartoli,De Fermo,Fonterenza) 
【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2024年7月その1(Ezio Cerruti,Possa,Bressan,Pierpaolo Pecorari,Natalino del Prete,Arianna Occhipinti,Vodopivec,Borgatta) 
【2024義捐ワインプロジェクト 第一弾】 
【新入荷】オータのアツアツ新入荷&2024年3月その2(Laserra,Vodopivec,Mlecnik,Il Cavallino,Pacina,De Fermo,Cantina del Barone,Cantina de’ll Angelo,Il Cancelliere) 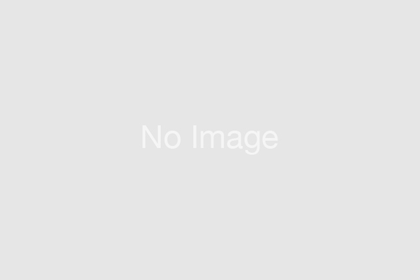
動画配信キャンペーン(ARPEPE, Vodopivec, De Bartoli)