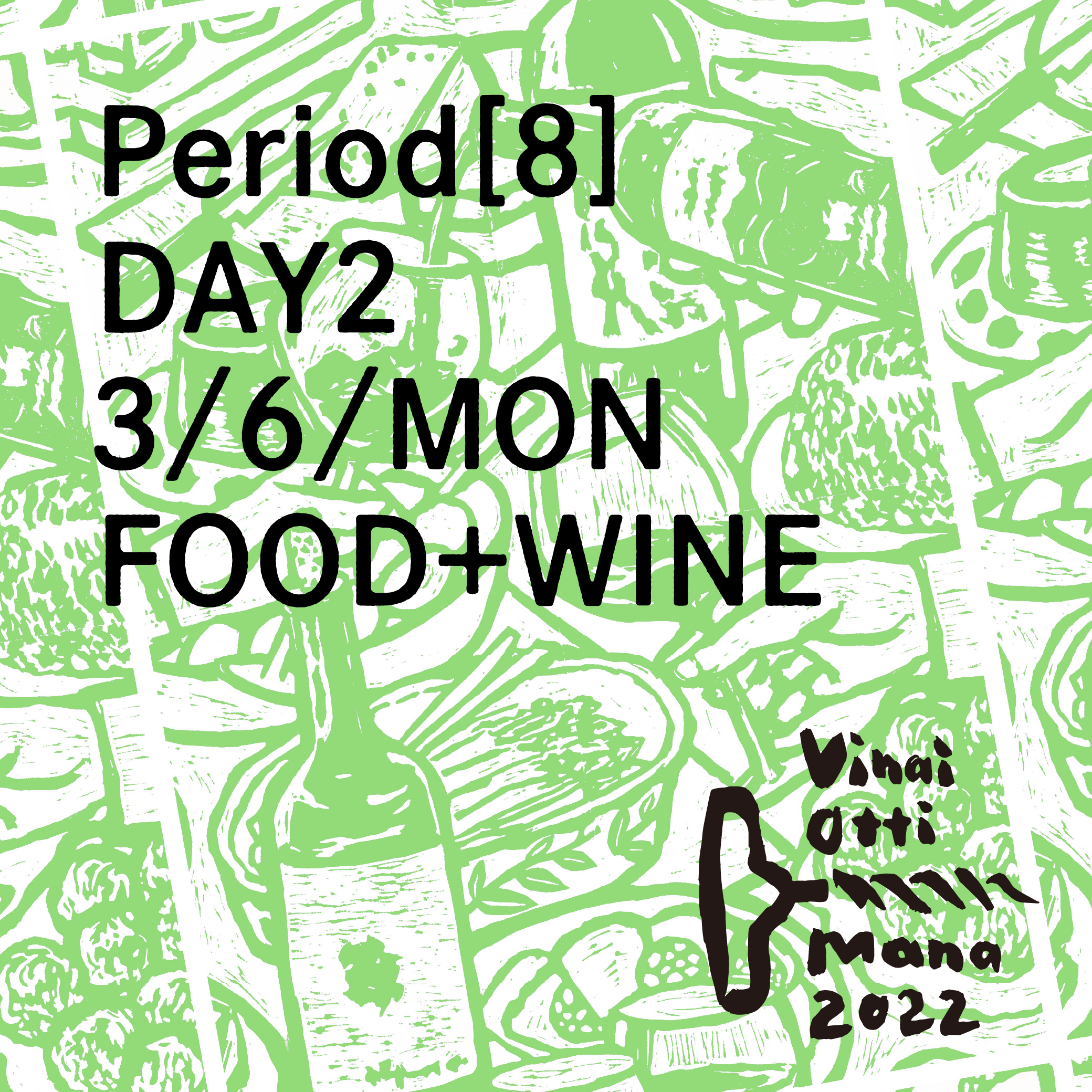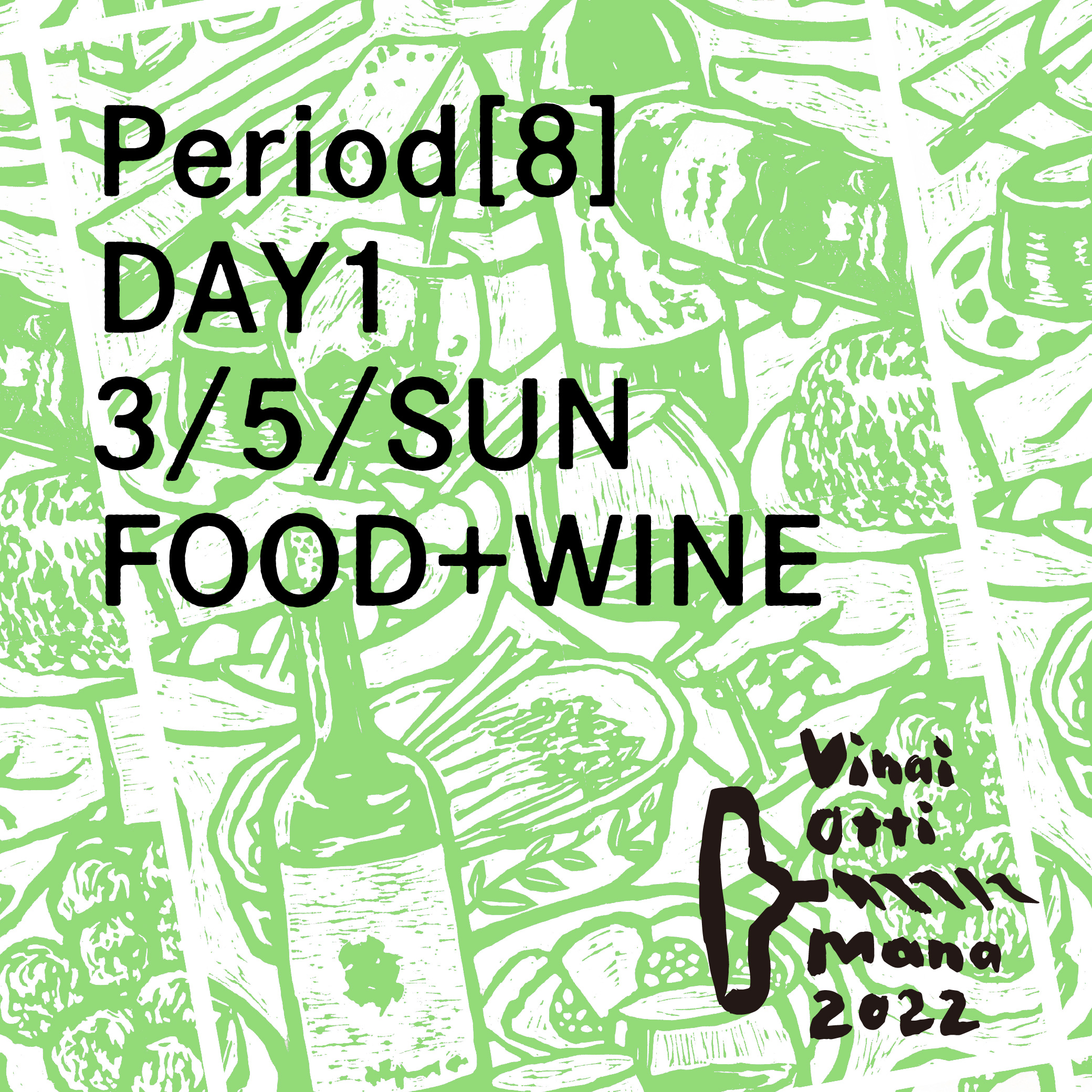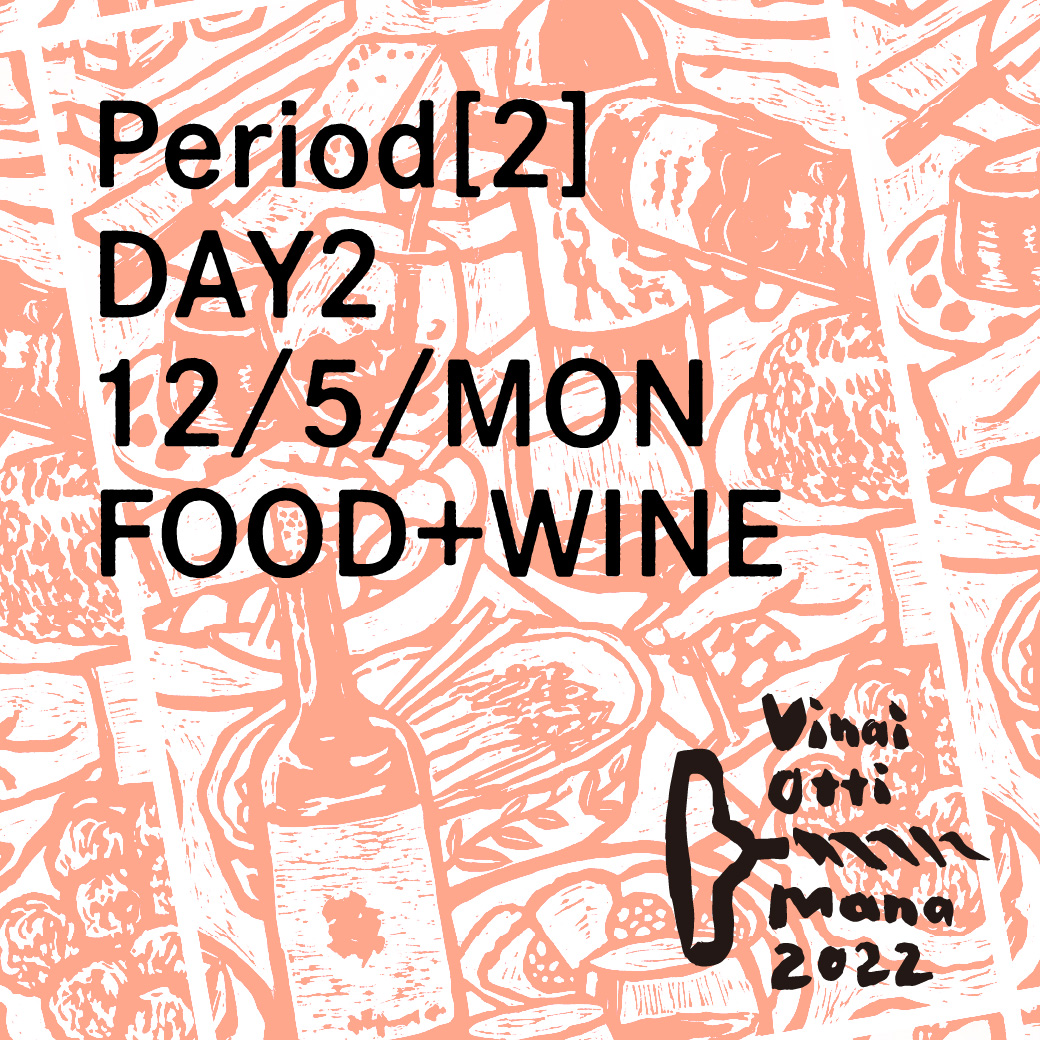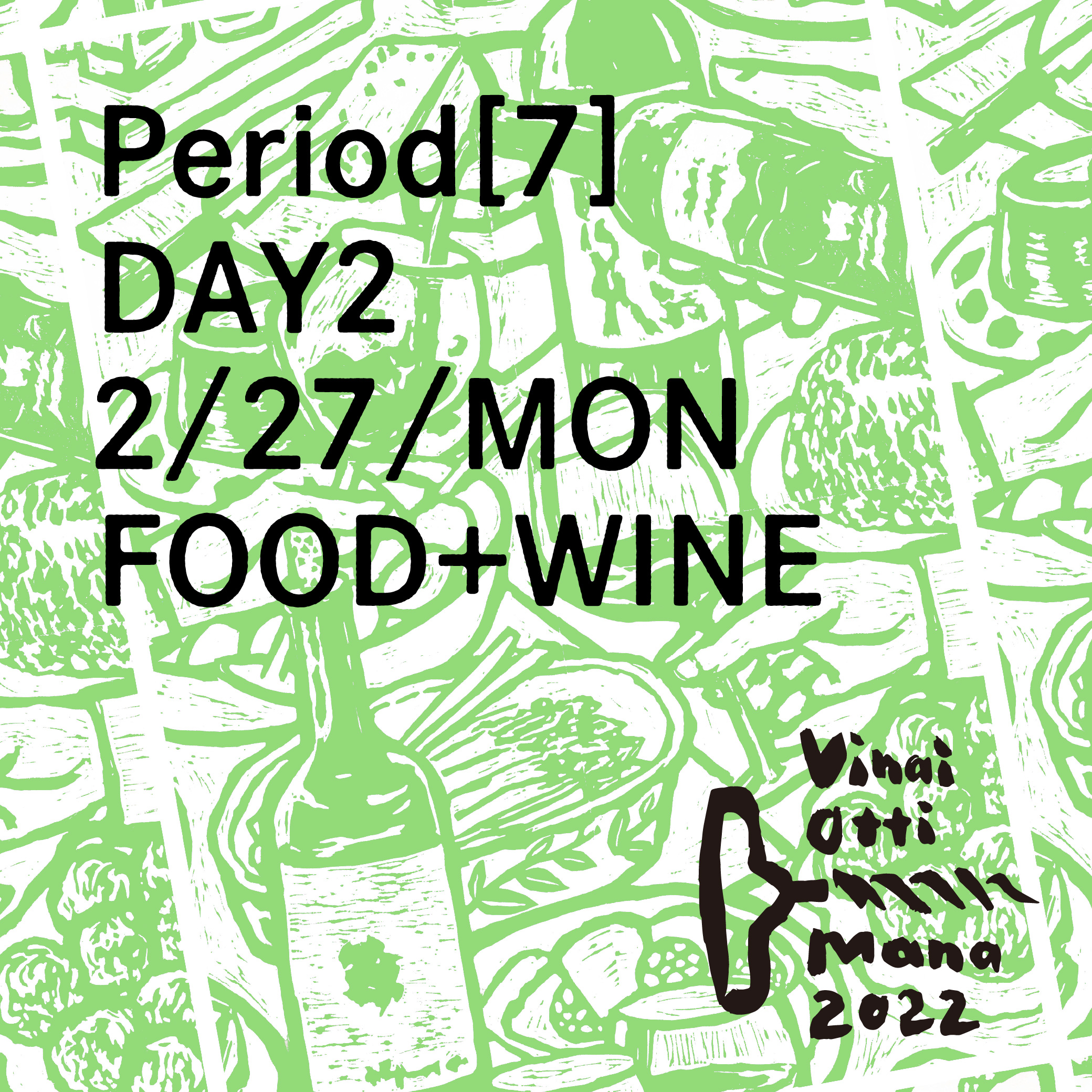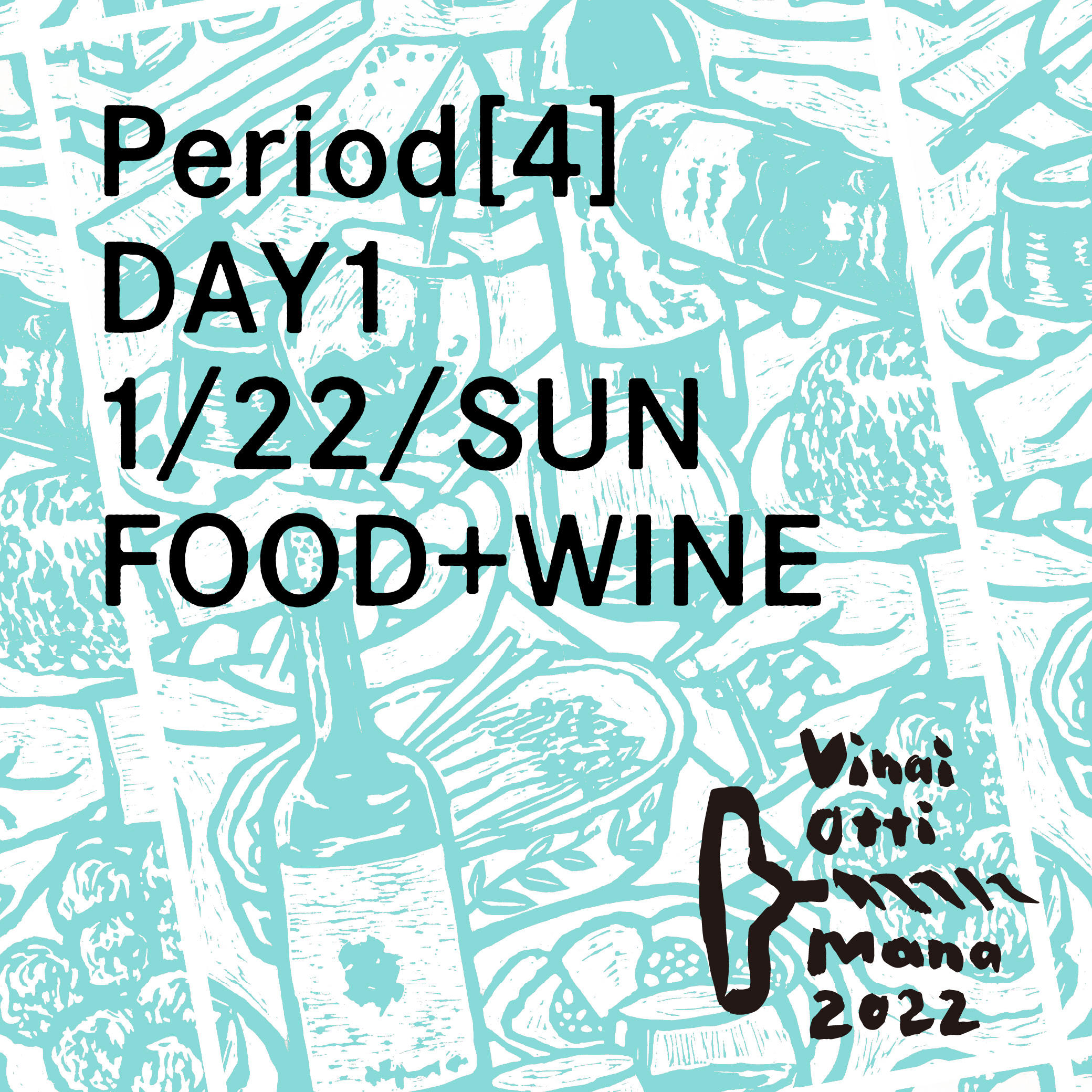<ヴィナイオッティマーナ2022 ~ピリオド1~>
【開催日時】
DAY1:2022年11月27日(日) 10:00~17:00
【会場】
だだ商店 だだ食堂(茨城県つくば市流星台56-3)
【タイムテーブル】
9:30 受付開始
10:00 開場
11:15- 造り手セミナー①<Vodopivec>
12:00-15:30 大食堂
16:00- 造り手セミナー②<Panevino>
17:00 終了
-参加造り手-
Domaine des Miroirs(フランス / ジュラ)
造り手:Kenjiro Kagami / 鏡 健二郎
2001年に渡仏、ジュラ県の南に位置するグリュス村に2011年から移り住み、ワイン生産者としての生活を始めた鏡夫妻。グリュス村を見下ろすブドウ畑には、1950年代までブドウが植えられていましたが、その後栽培放棄され森化しており、2005年以降再びブドウが植えられてからも一度も除草剤が撒かれていないため、二人にとってはまさに理想の環境でした。
ブドウの樹、畑の土、自生している草花、気候などを、自分たち自身で見て、触れ、そしてそれらの関係を注意深く自らの目で観察することでのみ、それらとの調和を図ったブドウ栽培が可能であること。そして、そのブドウからさまざまな要素が引き継がれたワインだけが、その土地やその年の個性を表現するだけにとどまらず、自身の思うワインというもの、ジュラでの生活の在り方や空気感さえも伝えてくれるという理念のもと、ワインを生産しています。ワインはすべて温度管理をせず、天然酵母での醗酵&熟成、無清澄&無濾過で瓶詰。
Panevino(イタリア / サルデーニャ)
造り手:Gianfranco Manca / ジャンフランコ マンカ
大地、人、その他の生命に対して最大限の敬意を払うべく、畑では一切の施肥を行わず、畑に自生する草を鋤き込むことで緑肥として利用しているほか、ボルドー液さえも使用せず、細かい粉末状の土と硫黄を混ぜたものを農薬代わりに6か月に1度(年、畑によっては一度も撒かない)する以外には畑には一切散布していません。ワイナリーでも、醸造からボトリングまでのすべての工程で一切の薬剤を使用しないポリシーの持ち主。
1986年から代々受け継がれてきた畑でのブドウ栽培を彼自身で手がけ始め、サルデーニャの土着品種(カンノナウ、ムリステッル、カニュラーリ、カリニャーノ、モニカ、モレットゥ、ジロ、モスカート、マルヴァジーア、ヴェルメンティーノ、セミダーノ、ヌラーグス) を栽培しています。品種や区画によっては樹齢100年を超えるものも。
ワイン生産以外にパン屋も生業としており、地元の無農薬の粉を使い、代々受け継いできた自然醗酵種をもとに薪釜でパンを焼いています。
Radikon(イタリア / フリウリ ヴェネツィア ジューリア)
造り手:Suzana Saksida / スザーナ サクシダ
1807年にフリウリ ヴェネツィア ジューリア州オスラーヴィアに居を構えたラディコン家。1980年より現当主サシャの父 故スタニスラオ(スタンコ)にワイナリーは委譲され、それまで量り売りしていたワインを自らボトリングするようになりました。
父スタンコの生まれ故郷であるコッリオは伝統的に白ワインの産地であり、赤のような複雑な味わいの白、それを出来る限り自然な醸造で造ることができないかと考え、祖父エトゥコが行っていたマセレーション(皮や種ごとの醗酵)という仕込みに着目。それは、収穫されたブドウを除梗もせずに皮や梗ごと木桶に放り込み、自重で潰れたブドウから出たジュースから自然と醗酵が始まり、果帽が上ってきたところで人力の圧搾機で絞り、皮や梗と果汁を分けるとモストはそのまま醗酵を続けていく、というシンプルな醸造でした。
1995年に土着品種であるリボッラ ジャッラこそ自分たちの土地に適合してきたブドウであるという考えから、実験的にマセレーションを行います。同年から畑での除草剤や化学肥料などの使用をやめ、化学薬剤の介在がない農法へと移行。タンニンを丸くするため、生産量の8~9割を占める白ワインは、樽できっちり3年寝かせ、ボトリング後もビンで3年寝かせているため、収穫年から約6年後にリリースされます(赤にいたっては収穫年から約10年)。
Trinchero(イタリア / ピエモンテ)
造り手:Ezio Trinchero / エツィオ トリンケーロ
アスティ県で一番初めにDOCワインの自家元詰めを行うための登記をした造り手であり、現当主エツィオは3代目に当たります。当初から、自然環境に最大限配慮した農業を心がけ、セラーでも人為的関与を極力避け、納得できないものはボトリングしないワイン造り&大樽での長期熟成を理想としてきました。
元々は40haもの畑を所有していましたが、もっとも条件の良い畑10haほどを残して他はすべて売却もしくは賃貸しに。残した畑のなかでも、最も重要な2区画がワイナリーに隣接した畑ヴィーニャ デル ノーチェとその隣のバルスリーナ。ノーチェは1920年代に、バルスリーナは1930年代にバルベーラが植えられた畑です。粘土質で肥沃な地質を持つアスティ地区ということもあり、施肥をしなくてもアルコール度数の高い、凝縮した果実味を持つワインができると考える彼は一切の肥料を撒かず、ボルドー液以外の化学的な薬剤に頼らない農業を行っています。
Vodopivec(イタリア / フリウリ ヴェネツィア ジューリア)
造り手:Paolo Vodopivec / パオロ ヴォドピーヴェッツ
イタリア北部の東端トリエステから北に15km、カルソ地方と呼ばれる石灰岩台地のほぼ中央にある小さな集落コッルドロッツァにヴォドピーヴェッツのワイナリーはあります。農業学校を卒業したパオロは、1994年に両親から畑を受け継ぎ、弟ヴァルテルとともに起業し、1997年から自家瓶詰めを始めました。
カルソは硬い石灰岩の岩盤で構成されているため土が極端に少なく、一般的にブドウ栽培に適さないと考えられてきましたが、パオロはミネラルが豊富なカルソという土地を表現するにはヴィトフスカこそが最良のブドウであると信じ、100年後にこの場所でブドウを栽培する人たちに向けカルソの持っている可能性を表現したいと考えています。地熱の影響でブドウがより凝縮しつつ、ボーラと呼ばれるこの地域特有の強風に枝を折られないように低めに仕立てたアルベレッロで、ボルドー液以外の農薬は使用せずに栽培を行っています。
収穫されるブドウとの対話のなかで醸造を試みるなかで、現在はアンフォラで醸し醗酵を行い、アンフォラと大樽で熟成を行うスタイルに落ち着いています。2011年に完成した、岩盤をくり抜いて作られたセラーは穴掘り以外の作業はパオロ一人で行い、大気やエネルギーを均等に循環させるため角(かど)がなく円を意識した造りで、電磁波の影響を受けることなくワインが静かに休める寺や神殿のような環境を目指して造られました。
-参加飲食店-
Due Mani (岩手)
料理人:Tomonori Ozawa / 小澤 智範
2010年、岩手・盛岡で8坪のスペースから始まった小さなイタリア料理店。店名の『Due Mani』は、イタリア語で「ふたつの手」の意味。“民藝”の考え方や“手仕事”のイメージから、「自分のやれる範囲で、責任を持って“まっとう”な料理を作りたい」そんな気持ちを込めて名付けられました。料理人の小澤さんは、地元岩手の生産者 自然農園ウレシパモシリさんでスペルト小麦を育てたり、茶道も習っていたり。
OLD NEPAL TOKYO (東京)
料理人:Ryo Honda / 本田 遼
古き良き文化を大切にし、そして常に新しさを取り入れ歩み続けるネパールの現在を体感できるレストラン。料理人の本田さんは、誰が食べてもネパール料理でありながら、誰が食べても心を揺さぶられる美味しさを追及しています。ネパールの食文化をより深く、より美味しく、より楽しく表現するために、年に数回必ずネパールを訪れ、数か月滞在しているそう。ディナーでは民族や地域性をテーマにしたストーリーのあるコース料理を、ランチではレストランスタイルのダルバートを提供。
villa aida (和歌山)
料理人:Kanji Kobayashi / 小林 寛司
料理人の小林さんは、イタリア トスカーナ州やカンパーニャ州などで料理の経験を経た後、地元である和歌山 岩出で元々は実家の田んぼだったところに、マダムの有巳さんとともにレストランをオープンしました。隣接する畑で休日には畑仕事をし、年間100種類以上の野菜やハーブを自分たちで露地栽培にて育てています。
仕事と生活が自然とともにある暮らし。庭にある果実の実でコンフィチュールや果実酒を作ったり、夏になるとたくさんのトマトを瓶詰して保存したり。輸入の高級食材ではなく、身近なふつうの素材を使って、イタリア料理やフランス料理をベースにしながら、どこの料理ジャンルにも属さない一皿、を目指して料理しています。現在は1日1組のお客さまを迎えて、ともに「食べ物の持つ時間」を共有することを大切に。
da olmo (東京)
サービス:Shinichi Harashina / 原品 真一
東京 神谷町で10年。シェフの北村さんが修行したなかで一番感銘を受けたという、北イタリア トレンティーノ アルトアディジェ州の郷土料理を軸に、国内の食材をこだわりを持って選び抜き、季節感溢れる滋味深い、また食べたくなる料理をコンセプトに提供しています。オーストリアやドイツの流れを汲む、保存性が高く手間ひまかけた「山の料理」が特徴。
サービスの原品さんは新宿御苑のタベルナ ロッサーナで立石滋さんに師事、8年間の修行後、新宿三丁目の客席70席のブリッコラをまかされる中で北村シェフと出会い意気投合、一緒にda olmoをオープンしました。斬新さや派手さを重要視せず、「主語はお客様」を合言葉に厨房、ホールが一体となった三世代で楽しめるレストランを目指しています。