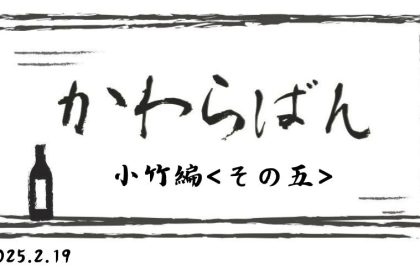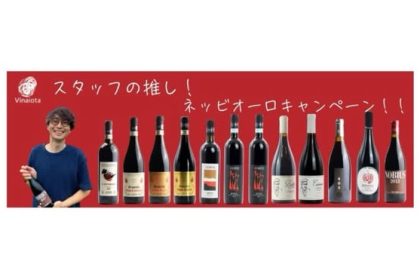ワインの起源 序章
わたくしオータ、ことワインに対してだけは情熱&好奇心を絶やすことなく、約30年に渡って真摯に向き合ってきたと自負しております(それ以外の事に関しては、叩いたら埃しか出てこないかもしれませんが…(笑))。
それは“ワイン道”とでも呼べそうな旅のようなもので、オータの人生の6割くらいの年月をかけた今現在でも、道半ばにさえ辿り着けていないのではないでしょうか。
(旅を)始めてから8年くらいの間は、その時代その瞬間の自分にとっておいしいワインを探すことが旅の目的だったと思うのですが、20年前にラ ビアンカーラのアンジョリーノを初めて訪問した時から、旅の主眼が“ワインのあるべき姿”を探し求めることへとシフトしていたのだと後から気が付きました。
嗜好などという言葉では片付けられない、揺るぎない何か…そんなワインの本質を知りに行くという壮大なツアーにいざ出かけてみると、そのツアー自体が、
テロワール(風土)
自然とヒト
文明文化
農業
ブドウ栽培(剪定から収穫まで)
醸造
微生物
食
身体
味
おいしさ
個性
などなど、ジャンル的にも非常に多岐に渡る観光スポット巡りで構成されていて、各々が深い関わりあいを持っているという事に思い至ります。そして、それぞれの観光スポットに対する見識を深めれば深めるほど、その奥深さ(無限、終わりのなさ)を痛感、本質には一向に近づけていないような気が長らくしていました。
ですが、ある日の“本質探し禅問答”の最中に、オータはとある仮説に辿り着きます。そしてその仮説の観点からワインの世界を見渡すと、多くの事がビックリするくらいすんなりと筋が通ることにも気が付きました。
それが、これから書いていきます「ワインの起源(ルーツ)」になります。
実際、本質という言葉を辞書で調べると、「物事の“根本”的な性質・要素」と書かれていますので、全く頓珍漢なわけではないのかと…。
「ワインの起源 その1」へ続く…
ここまでの文章を書くのに、なんと1週間以上の時間がかかってしまいました…(でも“その1”以降はサクサク書きます!)。学生時代、国語が不得意すぎたオータにとって、作文は非常にヘビーなお仕事。最近仲良くさせていただいている塗師にして文筆家なAさんはそんなオータに向って、「寝ている時に文章が浮かんできて、起きたらそれを文字に起こすだけで良い時がある。」などと、意味が分からないことを仰るんです…才能って残酷(笑)。