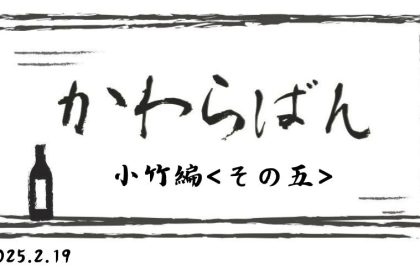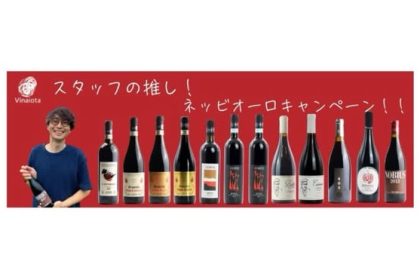ワインの起源 その1
皆さんは、「ワインの起源(=ワインがどのようにして生まれたか)」について考えたことがありますか?ただしここでオータがワインと呼ぶものは、偶発的であれ、意図的であれ、人が介在する中でできたものだけ、ということにします。
山に自生していた樹に生っていた果実が、何かの拍子で落ちて、潰れて、酵母と出逢い、醗酵したのがワインの起源だと言ってしまうのなら、自然発火で起こった山火事から逃げ遅れて命を絶たれた豚こそが豚の丸焼きの起源だと言っているようなものかと(笑)。
8000年ほど前にジョージアでワインが造られていた事は、発掘された遺跡などから明らかになっていますが、それは新石器時代にあたり、農耕や牧畜が始まったとされる時期でもあります。そして、その集落遺跡のそばの現在は森になっている丘が、当時ブドウ畑だったことも確認されたそう…。ですが、ここで発見されたのは、ワイン醸造とブドウ栽培がある程度の期間続けられてきて、それらが“文化”となった痕跡であって、オータが問うている“ワインの起源”は、醸造や栽培が定着する前の話。
少々脱線します。では、ワイン醸造とブドウ栽培のどちらが先に始まったのか?これに関しては、ほぼ間違いなくワイン醸造が先だったとオータは考えています。なぜかというと、ブドウという旬のある(=短期間しか食べることができない)食料を多量に手に入れるために栽培を始めたと考えるよりも、加工することで(果物よりは)保存性の高いワインを多く造るためにブドウ栽培を始めたと考える方が理に適っているから。干しブドウにしたら、保存性の高い食品にはなりますが、この当時のヒトにとってはむしろ主目的から遠ざかってしまうものだったのかと…(この“主目的”については、また後程!)。なんにせよ、食料としてその瞬間に食べる程度なら、山ブドウ(言うまでもなく山に自生する…)を採取するくらいで良かったのではないでしょうか。
で、また話を元に戻します。ワイン会とかに呼んでいただいた際、参加されている方たちにワインの起源ってどんなだったと思いますか?と質問をすると、
「とり過ぎてしまって、食べきれなかったものが醗酵しちゃった。」
「とってきたブドウをかごに入れっぱなしにしていたら、勝手に醗酵した。」
などといった答えが大半だったりするのですが、当時の時代背景等を考えると、少々的外れな気がしています。
まず“とり過ぎ”ですが、前述の通り、最初の“できちゃったワイン”は、ヒトが栽培したブドウではなく(→収穫=獲る)、自生する山ブドウ(→採集=採る)で造られたと踏んでおりますので、食べきれないほどの量を山で採る事自体、労力的にも大変な事だったでしょうし、“食べる事=生き延びる事”だったその当時に、“食べきれないほどの…”という概念が存在したとは想像できないオータがいたりします。つまり、ブドウとして“食べる事”以外の目的で大量に採集したのかと…。
そして、“放っておいたら勝手に醗酵した”ですが、アルコール醗酵は果肉に含まれる糖分が外界(微生物のいる世界)と出逢わない限りスタートしません。つまり、ブドウの房をそのまま放っておいても、(ブドウが潰れない限り)ワインになることはなく、風通しが比較的良い環境であれば、干しブドウになってしまいます。ブドウは自重程度で潰れることはありませんし、自然な重みで潰れるには、ブドウの上にブドウが大量に積み重なっている必要があります。そしてブドウを採取しに行く時に持っていく容器は、土器でなく蔓などで編んだ籠のようなものだったでしょうから、仮にその籠を放置し、籠の下のほうのブドウが少々潰れたとしても、液体は籠から流れ出てしまっていたでしょう。で、仮の仮にその流れ出たジュースや潰れたブドウが上手く醗酵し、ワインになっていたとしても、ヒトがワインの魅力に取り憑かれるのには量的に不十分だったでしょうし(笑)、流れ出たジュースがワインに変わる様に触発されて、ブドウをちゃんと潰してワインを造ろうと考えた…というのは、いささか無理がある気がします。
これらの事を総合すると、ワインの起源は、「ヒトは、山に行き、ブドウを大量に採取し、潰した。それが時間の経過とともに勝手に醗酵が始まり、ワインになった…。」といった感じだったという事になります。
では、なぜわざわざブドウを潰したのでしょう?ここで前述の“主目的”というポイントに戻ります。恐らく(というか間違いなく)、ヒトは“安全な水分”という観点からブドウに着目したのではないでしょうか。
糖質と水分こそが、生存を実現する2大要素であることは、誰しも疑問を挟む余地はないかと…。
(その2へ続く)