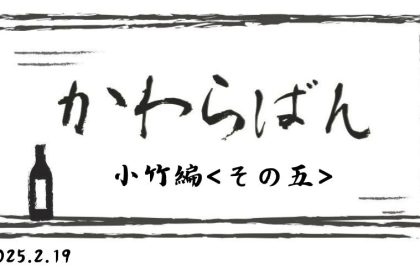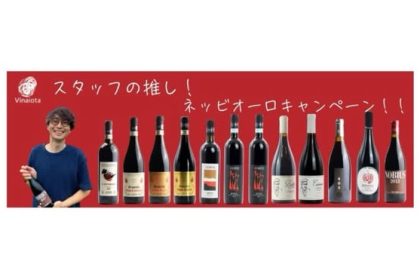ワインの起源 その2
“安全な水分としてのワイン”
リンゴやブドウのような果肉部分を食べるものであれ、アーモンドやクルミのように種子の仁を食べるものであれ、料理を覚えたり農耕を始めたりする遥か昔から、果物は、我々の命を支えた重要な食糧でした。そして果物が大切な糧であったことは、なにもヒトだけに限った話ではなく、それらを食すあらゆる動物にとっても一緒だったわけで、山でたわわに生る甘い芳香を放つ果物を見つけたのなら、他の動物に先を越される前に、食べられるだけ食べていたのではとオータは推測しています。お腹いっぱい食べたのに、果物がまだたくさん残っている…そういった場合、次の日に同じ樹のところに戻ってきたところで残っている保証は全くないわけですから、ヒトは食べきれなかったものを、その場に居合わせなかった家族や仲間のためであったり、後日食べる分として、持ち帰れるだけ持ち帰ったのではないでしょうか。
ですが、糖質、タンパク質、脂質そして各種ビタミンなど、生きていくために必要な栄養素をもたらす食糧という位置づけ(もちろん、各種栄養素など古代人ないし原始人の知る由のない事ではあるのですが…)でだけ果物を摂取していたのなら、そのまま食べるだけで、わざわざ果実を潰したりなどしなかったはず。となるとやはり、潰すことで出てくる液体部分に興味があったという事に…。
水分は、ほぼすべての動物にとって必要不可欠なものなわけですが、その当時主に飲用に使用されていたであろう川や湖沼の水が不純物や微生物などを含み、身体的にも負荷のかかるものであることに、ヒトは体感的に気が付いたのではないでしょうか。もちろん、我々現代人よりは遥かに頑強で野性的だったとは思うのですが、毒性のある重金属だったり、様々な病原菌などの溶け込んだ水は、その時代のヒトにとっても十分に危険なものだったでしょう。加えて、飲用に耐える水も溜め置いておくことで“腐る”ことも体験的に学習し、それと同時に果実に含まれる水分が(果)樹によって浄化&無菌化されたものだという事にも身体が気付いてしまった…。
そういったわけで、安全な水分な上に栄養まで摂れちゃうステキな液体を確保すべく、山へ果物を大量に採りに行くことに。果実を潰し、ジュースを容器で保存していたところ、とある日、液体からブクブクと泡が出ているではありませんか(=醗酵がスタート)!恐る恐る舐めてみたところ、ちょっとシュワシュワしていて、甘く、おいしい(=飲める=腐っていない)。毎日定点観測的に飲んでいく中で、日に日に甘さは減っていくような気がするが、相変わらず腐った雰囲気がないどころか、なんだかいい気分になる…。そしてそこからまた何日か経ったある朝、容器を見てみると泡が立っていない…。飲んでみると、甘さは皆無、そして数日前よりも気持ち良くなるのがちょっと早い気が…。
オータは、こんな感じでワインが生まれたのだと考えています。
水(分)として比較的長い期間健全さをとどめる上に、気持ち良くもなれる魅惑の液体を造るのが毎年の恒例行事になり、それを続けていくうちに、果汁を搾り取った後にそこらへんに捨てていた種から芽が出て、さらに何年かすると果実が生り始める…。実際、山に採りに行くのも大変だし、他の動物に食べられてしまって全く収穫できないこともあったりするし、だったら住まいの近くで育てちゃおうか?ブドウ栽培もこんな感じで始まったのではないでしょうか。
そもそも、なぜブドウだったのでしょう? 答えは簡単。果実が柔らかく、人力でも容易に果汁を絞ることができたから。リンゴで造るシードルは、圧搾機が開発されてから、普及していったのかと。
(その3へ続く)